看護師の心のSOS、コロナ禍で半数以上が精神的苦痛を抱えていた!

みなさんは、コロナ禍で働く看護師さんたちがどれほど大きなストレスと向き合っていたか、ご存じでしょうか?
この記事では、「看護師の精神的苦痛」に焦点を当て、その背景や原因、そして今できるサポートについて、最新の研究をもとにわかりやすく解説します。
「夜勤明けなのに家事も育児も休めない」「体調が悪いけど、現場が忙しくて休めない」――そんな経験、あなたやあなたの身近な看護師さんにもありませんか?
「なぜ看護師はこんなにも心が疲れてしまうの?」そんな疑問を持つ方も多いはず。
その答えは、社会的な支援の不足や“感情労働”、無理して出勤する“プレゼンティーズム”にありました。
(プレゼンティーズムとは、従業員が心身の不調を抱えながらも出勤し、業務を続けているものの、生産性が低下している状態を指します。)
この記事を読むことで、看護師の心の健康を守るために何ができるのか、具体的なヒントが手に入ります。
看護師の心の健康は、私たちみんなの健康にもつながる大切なテーマです。ぜひ最後まで読んで、身近な人を支えるヒントを見つけてください!
目次
要点
- コロナ禍の看護師の約54%が精神的苦痛を経験
- 社会的支援の不足や感情労働の負担、プレゼンティーズムが精神的苦痛を悪化させる
コロナ禍で見えた看護師の「心の現場」。約半数の看護師が「精神的にしんどい」と感じていた
イランの9つの病院で行われた最新の調査によると、看護師の53.8%が精神的苦痛を感じていることがわかりました。
特に、女性・契約社員・経験の浅い方ほど、その傾向が強いという結果に。
看護師の1年目は辛いとはよく言われていますが、苦痛を感じやすい要素として上がっていますね。
| 属性 | 精神的苦痛の割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 女性 | 高い | 感情労働負担増加 |
| 契約社員 | 高い | 福利厚生の不安定さ |
| 経験年数が浅い | 高い | ストレス対処力の差 |
| 社会的支援が多い | 低い | 精神的苦痛の軽減 |
こんな場面、思い当たりませんか?
- 夜勤やシフト勤務で生活リズムが乱れ、常に疲れが抜けない
- 患者さんやご家族の前では笑顔を絶やせない(=感情労働)
- 体調が悪くても「人手が足りないから」と無理して出勤(プレゼンティーズム)
このような毎日が続くと、「もう限界…」と感じてしまうのも無理はありません。
支えがあると心が軽くなる

研究では、「周囲からのサポート」が多い人ほど、精神的な苦痛が少ないことも明らかになりました。
たとえば――
- 「困ったときに相談できる同僚がいる」
- 「家族が話を聞いてくれる」
- 「上司がシフトを柔軟に調整してくれる」
こうした小さな支えが、実は大きな力になるんです。
無理しすぎはNG!自分を守るためにできること
- つらいときは「無理しない」「誰かに頼る」勇気を持ちましょう
- 家族や友人が看護師なら、「大丈夫?」と声をかけてあげるだけでもOK
- 職場の管理者は、シフトや雇用形態への配慮、チームビルディングなどの取り組みを
「がんばりすぎない」「ひとりで抱え込まない」ことが、心の健康を守る第一歩です。
まとめ:看護師の心の健康を、みんなで守ろう
この記事では、コロナ禍で看護師の半数以上が精神的苦痛を感じていたこと、
その背景には社会的支援の不足や感情労働、無理な出勤があることをお伝えしました。
支えがあるだけで負担は少なくなります。ちょっと気にかけてもらうだけでも気持ちが楽になることは看護師でなくてもありますよね。
ぜひ、あなたの身近な看護師さんや医療従事者に「ありがとう」「大丈夫?」と声をかけてみてください。
みんなで支え合うことで、心も体も元気な社会をつくりましょう!
参考文献
- 論文タイトル・リンク:
Relationships between nurses’ perceived social support, emotional labor, presenteeism, and psychiatric distress during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40307867/
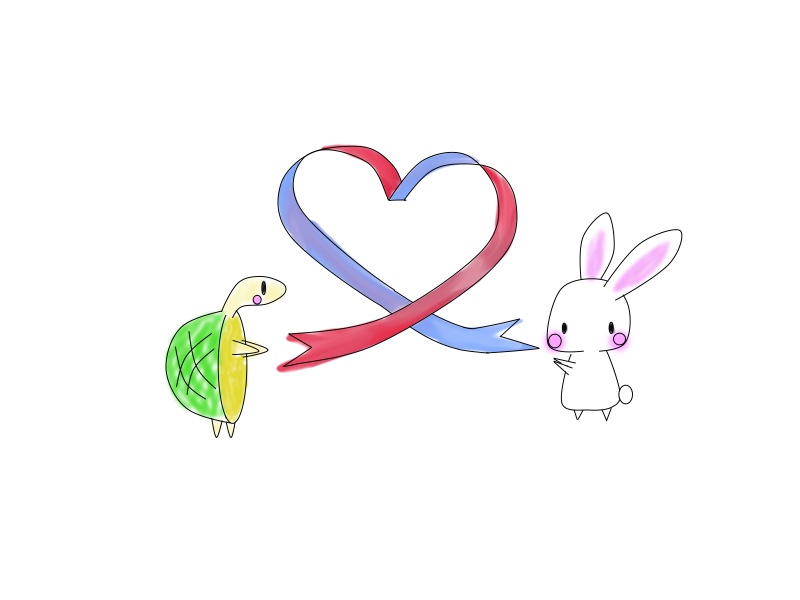






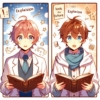





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません