【看護学生の不正行為】“ちょっとしたズル”が命を脅かす?教室と臨床の現実

「なんでそんなことまで?」
学生時代、同僚の看護学生が“ちょっとしたズル”をしているのを見たこと、ありませんか?
レポートの手伝いを頼まれたり、試験中にチラッと目が合ったり……「まぁ、あるよね」で済ませてきたかもしれません。
でも、もしそれが、臨床の現場でも続いていたら?
命を預かる立場で、「ちょっとした嘘」が積み重なることの怖さ――。
この記事では、看護学生の「不正行為」の実態と、その背景にある“心理”をやさしく解きほぐしていきます。
目次
🔍 学生時代の不正は、臨床でのリスクにもつながる
看護学生の「教室での不正行為」は、将来的に「臨床現場での不正」にもつながる傾向があります。
ごく小さな不正でも、患者の安全を脅かすリスクがある以上、学生時代から誠実さを育てることが大切です。
🧪 教室での不正行為、なんと9割以上が経験
クロアチアの研究では、446人の看護学生のうち91.3%が教室で不正行為を2回以上したと回答しています。
私が新人看護師だった頃、ある後輩が「試験でカンニングしちゃって…」と打ち明けてくれたことがありました。
本人は軽い気持ちだったようですが、こうした“小さなズル”が臨床に持ち込まれるとしたら――そう思うと怖くなりました。
📘 そもそも「不正行為」ってどんなこと?
この研究では以下のような行為が「不正」に分類されていました:
- 📄 試験中のカンニング(カンペ使用・回答のやりとり)
- 🗂 他人にレポートを書いてもらう
- 🧏♀️ 回答の共有や合図
- 📚 過去問の不正入手と利用
🏥 臨床現場の不正は“命に関わる”
32.5%の学生が臨床実習でも不正を経験していたという結果も出ています。
例えば…
- 🩺 バイタルを測らず「正常」と記録する
- 🧼 手洗いせずにケアに入る
- 🧾 記録をごまかす
これらの行為は、感染症や医療ミスに直結する重大なリスクです。
🧠 不正行為の“心理的な背景”とは?
なぜ看護学生は不正行為をしてしまうのでしょう?
研究では、以下のような心理要因が示されました:
- 社会的学習理論:周りがやっていると自分もやってしまう
- 合理的選択理論:「バレなければ得」と判断する
- 中立化理論:「みんなやってるし…」と正当化してしまう
私も学生の頃、友人のズルに気づきながら見て見ぬふりをしたことがあります。止める勇気があれば、違う未来があったのかもしれません。
🌱 今日からできる小さな一歩
- ❓「これってズルかも?」と感じたら、まず立ち止まる
- 💬 気づいたことはやさしく声に出す(例:「記録、一緒に見直してみようか?」)
- 🧑🏫 先生や先輩に相談する
私はある学生の記録ミスに気づいたとき、「確認してみようか」と声をかけることで、自然に改善へと導けました。
📝 まとめ|“小さな不正”が将来を左右する
- 看護学生の9割以上が教室で不正行為を経験
- 臨床でも3割以上が不正に関与
- 日常のズルが命のリスクに直結する
- 「気づき」と「声かけ」で未来は変えられる
👉 「小さなズル」が未来の看護を左右するということですね。
あなたの声が、患者の命を守るきっかけになるかもしれません。
✅ 参考文献
- Lovrić, R., & Žvanut, B. (2022). Profiling nursing students’ dishonest behaviour in classroom versus clinical settings. Nursing Ethics.
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35616389/
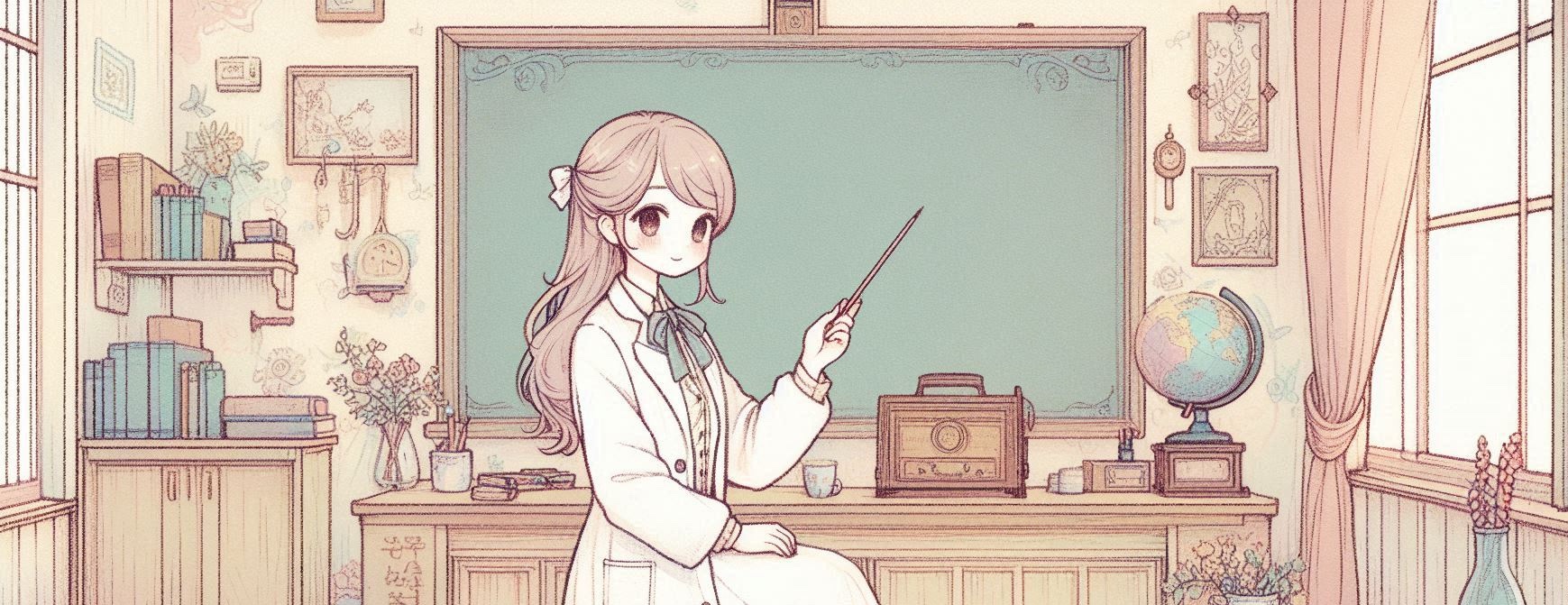






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません