薬物依存者はなぜ自殺を考える?10,000人調査で明らかになった6つのリスク要因

目次
薬物依存の人が「死にたい」と感じる本当の理由
「薬をやめればすべて解決する」――本当にそうでしょうか?
この記事では、メタンフェタミン(覚せい剤)依存症の人が自殺を考える背景にある「6つの要因」を、中国・広東省の10,000人調査から解説します。
「依存症の家族が急に『消えたい』と言い出した」「トラウマを抱える人が依存症になりやすいと聞くけど…」
そんな経験や疑問を持つ方も多いはず。
最新の研究によると、自殺念慮は「薬物の量」だけでなく「子どもの頃の体験」や「性格」が複雑に絡み合って生じることがわかっています。
この記事を読むと、依存症の背景にある“見えない要因”を理解し、適切な支援のヒントが得られます。
薬物の量だけでは説明できない
例えば、30代のAさんはメタンフェタミンを常用していましたが、使用量が少ないのに「死にたい」と頻繁に口にします。
調査では、1回の使用量が多い人ほど自殺リスクが5.5倍に跳ね上がることが判明。しかし、それだけが原因ではありませんでした。
子どもの頃の虐待が影を落とす

Bさんは、子どもの頃に身体的虐待を受けていました。
研究によると、身体的虐待経験があると自殺リスクが3.4倍に。
「薬で現実から逃れたい」という気持ちの背景に、過去のトラウマが潜んでいるケースが多いのです。
性格より環境が影響する
「神経質な性格がリスクを高める」と考えられがちですが、実際には「情緒的ネグレクト(2.8倍)」や「低学歴(1.3倍)」などの環境要因の影響が大きいことがわかりました。
リスク要因比較表:
| リスク要因 | オッズ比 |
|---|---|
| 1回使用量 | 5.52倍 |
| 身体的虐待 | 3.43倍 |
| 情緒的ネグレクト | 2.77倍 |
支援のカギは“過去のケア”
依存症の人を支援する際は、
- 「なぜ薬に頼るようになったのか」背景を考える
- 「意志が弱い」などと責めない
- 専門機関と連携してトラウマケアを検討する
といった対応が大切です。
まとめ:依存症は「個人の問題」ではない
この記事でお伝えしたのは、「薬物依存の自殺リスクは、生育環境や社会要因と深く結びついている」という事実です。
- リスク要因の60%は「子どもの頃の体験」が占める
- 支援には薬物治療だけでなくトラウマケアが必要
「依存症=自己責任」という偏見を捨て、社会全体で支える視点を持ちましょう。
まずは地域の依存症支援窓口の情報を調べてみてください。
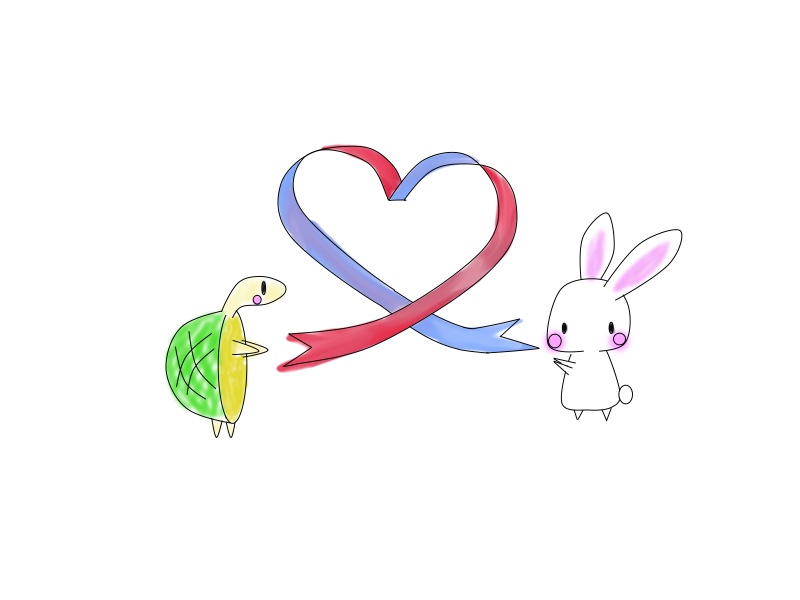








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません