精神科ジャーナルは“時代の鏡”――アメリカとイギリスで異なる心の治し方

この記事では、精神医学の「主流モデル」がアメリカとイギリスでどう変わってきたのか、学術誌の分析から分かった“心の治し方”の歴史と今後のヒントをやさしく解説します。
うつ病や不安障害の治療法を調べると、薬が効くという話もあれば、カウンセリングや社会的支援が大事という話も。いったい何が“正解”なんだろう?と迷ったことはありませんか?
実は、精神医学の主流は“科学の進歩”だけでなく、社会や時代の流れで大きく変わってきたんです。
“心の治し方”の歴史と多様性を知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
要点
- ポイント1:精神医学には「生物医学モデル」「心理学モデル」「社会モデル」の3つの主流があり、時代や国によってどれが中心かが大きく変わってきた。
- ポイント2:アメリカでは時代ごとに主流モデルが大きく変化しやすい一方、イギリスでは複数モデルが共存しやすい傾向がある。
時代や国で変わる“心の治し方”
たとえば、アメリカでは「薬が第一!」という時代もあれば、「社会的なサポートが大切!」と大きく舵を切った時期も。一方イギリスでは、薬・カウンセリング・社会支援がバランスよく並ぶ“ごった煮”状態が続いています。
身近な例で言えば――
・「アメリカの映画ではすぐ薬が出てくるけど、イギリスのドラマはグループセラピーや地域の支援がよく描かれる」
・「日本でも“薬だけ”から“話を聴く”や“社会とつながる”支援が増えてきた」
こんな違い、感じたことはありませんか?
学術誌から見えた“時代の流行”

アメリカ(AJP)とイギリス(BJP)の代表的な精神医学誌を、1940年代・60年代・2000年代で分析。
・アメリカは「生物医学モデル(薬や脳の研究)」→「社会モデル(環境や支援)」→再び「生物医学モデル」へと大きく揺れ動き
・イギリスは、どの時代も「生物医学・心理学・社会モデル」がバランスよく共存
つまり、「今の主流=絶対の正解」じゃなく、時代や場所で“正解”は変わることが分かったのです。
生物医学・心理学・社会モデルはバイオ・サイコ・ソーシャルと訳され、それぞれのバランスが関係することが最近では言われています。
いま私たちにできること
薬もカウンセリングも社会的なサポートも、どれか一つにこだわる必要はありません。
「自分や家族に合う方法を、柔軟に選んでいい」――これがこの記事の一番のメッセージです。
まとめ:心のケアは“多様でOK”な時代!
「心の治し方」は一つじゃない。時代も国も、そしてあなた自身も“正解”を選んでいい。
精神医学の主流は時代や国で大きく変化します。また、科学だけでなく社会や文化も影響しており、住む地域や社会情勢でも異なります。
個人的には時代に先行して効率の精神科病院を廃止したイタリアの時代の変遷なども非常に好きです。
今の“常識”にとらわれず、あなたや大切な人に合う心のケアを探してみてください!
参考文献
- 論文タイトル・リンク:
Psychiatric journals as the mirror of the dominant psychiatric model
https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/psychiatric-journals-as-the-mirror-of-the-dominant-psychiatric-model/1931DF408980CE3DA30361A329715747
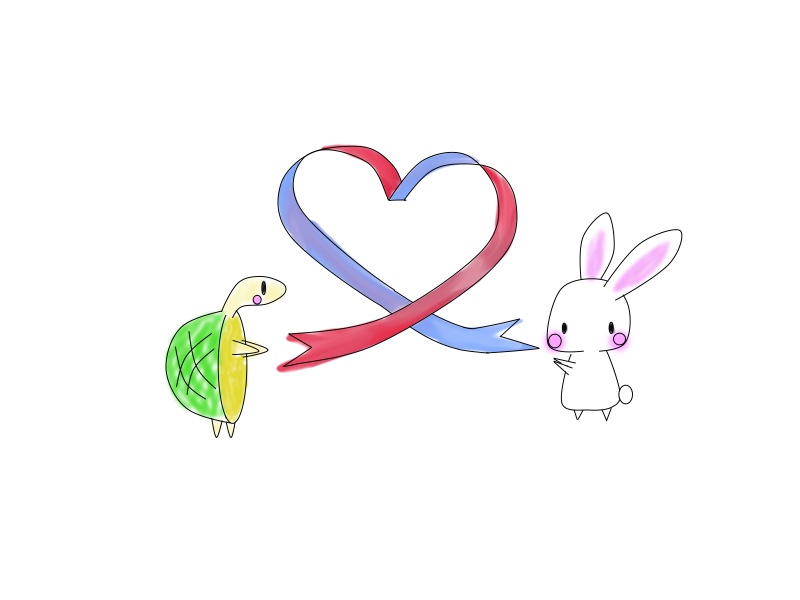

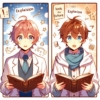









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません