“自分ならできる”は通用しない?脳が他人の能力を見積もる驚きのメカニズム

「この人ならきっとできるはず」「自分の方が得意かも」――そんなふうに、友達や同僚の“できる・できない”をなんとなく予想したこと、ありませんか?
でも、実はその予想、私たちの脳がある“クセ”で判断しているって知っていましたか?
今回ご紹介するのは、まさにそんな「他人の能力をどう見積もるか」に関する最新の脳科学研究。
自分と相手の得意・不得意、どうやって見抜いているのか?
意外な脳の働きや、日常で役立つヒントもたっぷりお届けします!
どうしてこんな研究をしたの?

「この仕事、あの人ならサクッとできそう」「あの子にはちょっと難しいかも…」なんて思った経験、一度はあるはず。
その“なんとなく”の予想、実は私たちの脳が、あるクセで判断していることが最新の研究で分かってきました。
しかしこの仕組み、実は自分より不得意な相手には有効ですが、自分より得意な相手にはうまく働かないことが明らかになりました。
実験ってどんなことしたの?

今回の研究では、参加者に「自分」「自分よりちょっと得意な人」「自分よりちょっと苦手な人」の3人で、誰が問題を解くのが一番いいかを考えてもらいました。
たとえば、クイズ番組で「この問題、誰が答える?」と作戦会議してるイメージです。
そのときの脳の動きをfMRIという機械で調べたり、さらに「前外側前頭前野(alPFC 47)」という脳の一部をピンポイントで“お休み”させて、判断がどう変わるかもチェックしました。
ちょっとSFっぽいですが、これで「脳のどこが他人の能力を見積もるのに関わっているか」が分かるんです。
実験の結果!

面白いことに、私たちの脳は「自分よりちょっと苦手な人」には、自分の感覚をうまく当てはめて予想できるのですが、「自分より得意な人」にはその方法が通用しません。
たとえば、あなたが料理が得意で、友達があまり料理をしないタイプだったら、「このレシピ、あの子には難しいかも」と正しく判断できる。でも、プロの料理人が相手だと、「どれくらいスゴイの?」とピンとこなくなり、見積もりがズレちゃうんです。
しかも、その“自分の感覚を当てはめる”力には、脳の特定の場所(alPFC 47)が深く関わっていることも判明。この場所を一時的に“お休み”させると、他人の能力をうまく予想できなくなる、という結果も出ました。
日常でどう役立つ?

つい「自分基準」で他人をジャッジしがちですが、特に自分より得意そうな人には、実績や周りの評価も参考にしてみましょう。
「自分には無理だから、あの人もできないだろう」と決めつけるのは、もったいないかもしれません。
まとめ
「自分の感覚で他人の能力を見積もるとき、実は得意・不得意で精度が変わる!」という脳の不思議なクセについて解説しました。
他者の能力を見積もるとき、自分より不得意な人には自分の感覚が役立つけれど、得意な人にはそれだけじゃダメ。客観的なデータや周囲の評価も参考にするのがポイントです!
「自分ならできる」だけじゃなくて、「この人はどうだろう?」と一歩引いて考えてみる――それだけで、もっと良いチームワークや人間関係が築けるかもしれません。
ぜひ、今日から身近な人の“できる・できない”を見積もるときに、この記事の内容を思い出してみてください!
参考文献
- 論文タイトル:Asymmetric projection of introspection reveals a behavioural and neural signature of social metacognition(Nature Communications, 2024)
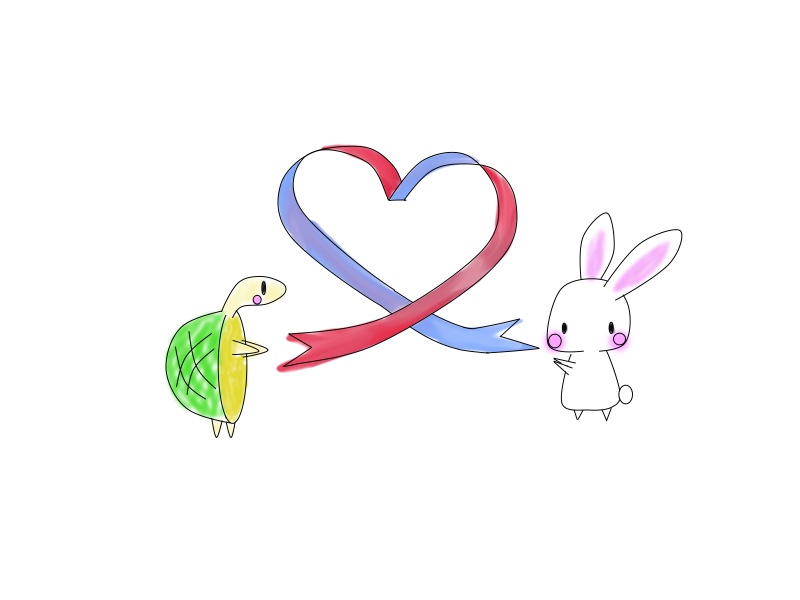

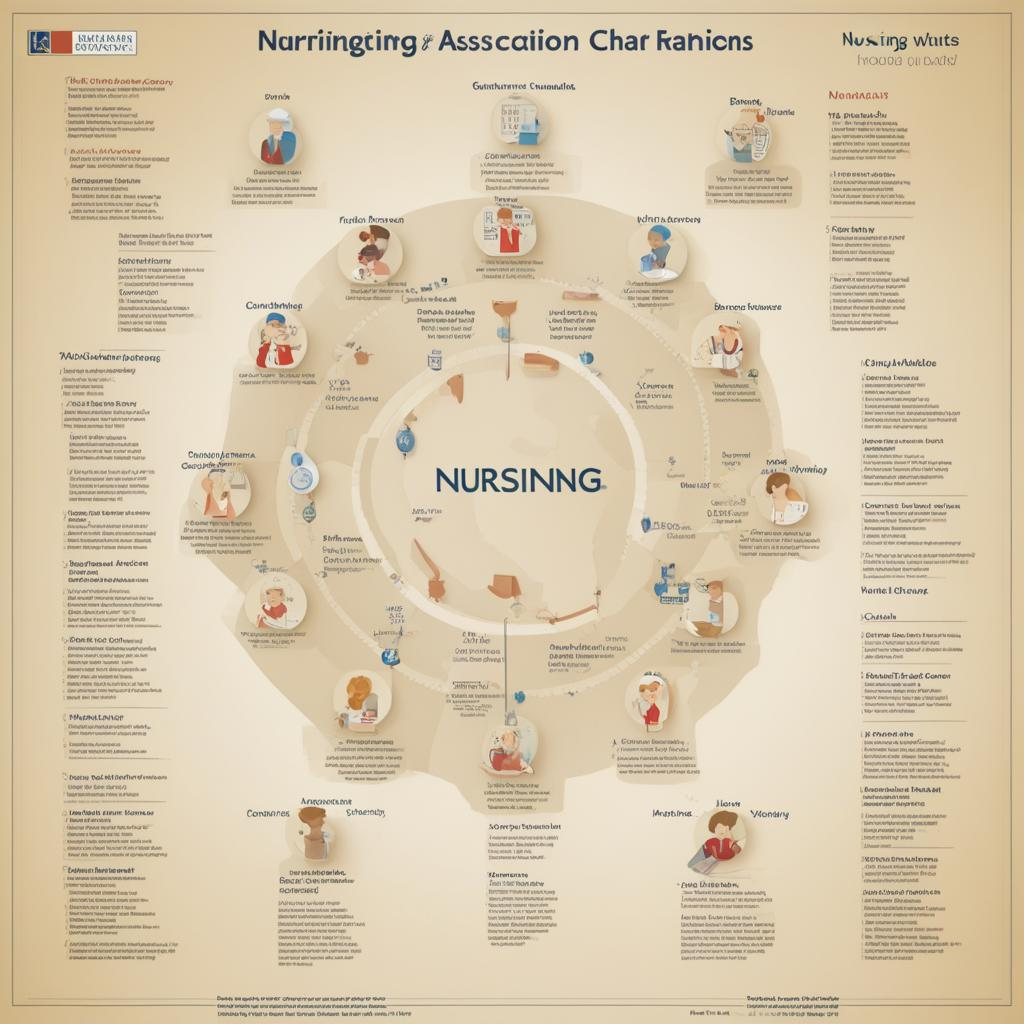










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません