心理学者の“考え方のクセ”が学問の対立を生む?7,900人調査の意外な事実

「同じデータを見ているのに、専門家の意見が真っ二つに割れるのはなぜ?」
この記事では、心理学の世界で起きる論争の背景に「研究者自身の考え方のクセ」があることを、7,900人調査から解説します。
例えば、大学でこんなシーンを経験したことはありませんか?
▶︎ A教授「この理論は時代遅れだ!」
▶︎ B教授「いや、まだ検証の余地がある!」
実はこの対立、データだけではなく「研究者の性格」も関係していることが最新研究で判明しました。
読み終える頃には、科学の論争が“人間らしい営み”だと腑に落ちるはずです。
要点
- 心理学の論争は“データ”だけでなく、研究者自身の認知的特徴によっても生じている
- 研究者の「曖昧さへの耐性」や思考傾向が、研究テーマや結論の違いにつながる
目次
実験でわかった「意見が割れる2大理由」
研究チームは、7,973人の心理学者にアンケート調査を実施。
「曖昧さへの耐性」 と 「白黒つけたがる傾向」 が、研究スタイルにどう影響するかを分析しました。
具体例:2人の研究者の違い
- Dr. 曖昧OK:新しい理論が好き/「答えは一つじゃない」と考える/複雑なデータを好む
- Dr. 白黒派:実証データ重視/「明確な結論」を求める/シンプルな分析を好む
この違いが、「どんなテーマを選ぶか」「どう解釈するか」 に直結していたのです。
研究テーマは“性格”で決まる?
調査結果を簡単に表すと――
| 研究者のタイプ | 選びがちなテーマ | 意見の傾向 |
|---|---|---|
| 曖昧OK派 | 未解決問題 | 「可能性は多様」 |
| 白黒派 | 実証検証 | 「結論はこれだ」 |
例えば、「AIの感情」を研究する場合…
- 曖昧OK派:「人間らしさの定義は流動的」と主張
- 白黒派:「感情の数値化が必要」と反論
科学の進歩は“多様性”がカギ

面白いのは、両者の対立が学問を発展させているという点。
「曖昧OK派」が新しい仮説を提案し、「白黒派」が実証する――このサイクルが心理学を進化させています。
まとめ:意見の違いは“個性”と受け止めよう
この記事のポイントをまとめると…
- 科学の論争はデータだけでなく「人間のクセ」も影響する
- “曖昧OK派”と“白黒派”の共存が学問を豊かにする
次に意見が対立したときは、「この人らしい考え方なんだな」 と受け止めてみてください。きっと議論が深まりますよ!
参考文献
- 論文タイトル・リンク:
Differences in psychologists’ cognitive traits are associated with scientific divides
https://www.nature.com/articles/s41562-025-02153-1
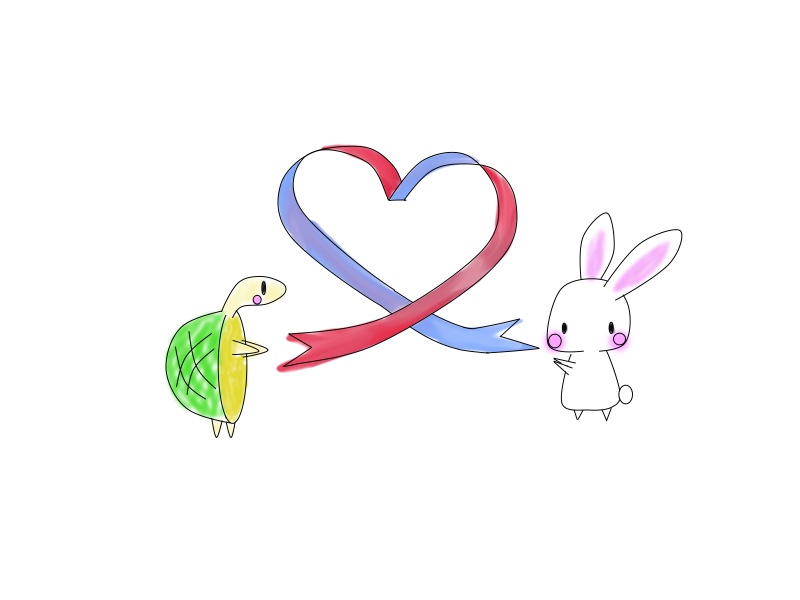










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません