【体験談】複数資格を取りすぎて疲れてしまった私が学んだ「本当に必要な資格の見極め方」

目次
📚 また資格の勉強?もう疲れちゃった…そんなあなたへ
「今度は何の資格を取ろうかな…」スマホを見ながら、また新しい通信講座の広告をタップしている自分に気づいて、ふと疲れを感じたことはありませんか?
私も現役看護師として働きながら、保育士、養護教諭、精神保健福祉士と次々に資格を取得してきました。でも正直に言うと、「あの時、もう少し考えて取り組んでいれば…」と後悔することも多いんです😅
夜勤明けにテキストを開いて眠い目をこすりながら勉強したり、休日も図書館にこもって過去問を解いたり。気づけば「資格のための勉強」に追われて、本当にやりたいことを見失っていた時期がありました。
もしあなたも「資格をたくさん持ちたいけど、なんだか疲れてしまった」という気持ちを抱えているなら、今日の記事がきっと参考になります✨
🎯 結論:資格疲れの原因は「目的の見失い」にあり!
複数資格で後悔してしまう一番の理由は、「なぜその資格が欲しいのか」という本当の目的を見失ってしまうことです。
資格取得自体は決して悪いことではありません。でも「とりあえず持っていれば安心」「みんな持ってるから私も」という気持ちで始めると、かえって心の負担が重くなってしまうんですね。
今日は看護師・心理学を学んできた私の実体験と、脳科学・心理学の知見をもとに、「本当に必要な資格の見極め方」をお伝えします!
🧠 なぜ「資格コレクター」になってしまうの?脳科学で解明!
📱 SNSを見ると焦ってしまう心理の正体
朝のコーヒータイムにInstagramを開くと、同期が「新しい資格取りました!」って投稿してる。LinkedIn見ると「○○検定合格」の文字が並んでる…。
「私も何かしなきゃ💦」
この焦りの正体、実は脳科学的に説明できるんです。
人間の脳には「損失回避バイアス」という仕組みがあります。簡単に言うと、「何かを失う恐怖」が「得られる喜び」の2倍以上強く感じられる心理現象のことです。
📊 損失回避バイアスの例
- 「あの資格を取らないと置いていかれる」← 損失への恐怖
- 「資格を取ったら嬉しい」← 獲得への喜び
🔍 結果:恐怖の方が2倍強く感じられる!
💝 HSP気質さんは特に注意!敏感な心が招く「やらなきゃ病」
私自身、HSP(Highly Sensitive Person:とても敏感な人)の気質があるのですが、周囲の期待や変化を人一倍敏感に感じ取ってしまいます。
HSPさんあるある:
- 上司に「○○の資格があると良いね」と言われると断れない
- 同僚が勉強している姿を見ると「私もやらなきゃ」と思ってしまう
- 患者さんや子どもたちのために「もっと知識をつけなければ」と自分を責める
実際、保育現場でも「英語ができる保育士さん」「発達支援に詳しい保育士さん」など、求められるスキルがどんどん増えています。真面目で責任感の強い人ほど、「全部できるようになりたい」と思ってしまうのは自然なことなんです。
🔄 マルチタスク学習が逆効果になる理由
「同時にいくつも勉強した方が効率的!」と思いがちですが、実は脳科学の研究では真逆の結果が出ています。
🧠 脳科学のデータ:
- マルチタスク学習は記憶の定着率が40%低下
- 一点集中学習の方が理解度が70%向上
- 複数同時学習は達成感も得にくい
私も以前、看護研究をしながら心理学のテキストを読み、同時に保育士の過去問を解いていた時期がありました。結果、どの分野も中途半端な理解で終わってしまい、「勉強しているのに身についていない」という無力感に苛まれました😔
👩⚕️ 「インポスター症候群」に陥りやすい専門職の心理
専門職として働いていると、「もっと知識がないとプロとして恥ずかしい」というプレッシャーを感じやすくなります。
これは心理学で「インポスター症候群」と呼ばれる状態。自分の能力に自信が持てず、「相手を騙しているのではないか」「いつかバレてしまう」「もっと勉強しないと」と感じ続けてしまう心理状態です。
私の体験談: 養護教諭の勉強中、不登校の生徒さんの相談を受けた時のこと。「児童心理や不登校支援を知らないで相談に乗って良いのだろうか」と不安になり、慌てて児童心理学の勉強を始めました。
でも実際は、その生徒さんが求めていたのは専門知識ではなく「話を聞いてくれる大人」だったんですよね。知識よりも、寄り添う気持ちの方がずっと大切だったと今では思います。
✨ 今日から実践!「資格疲れ」を解消する3つの方法
🎯 方法1:「なぜその資格?」を3つの視点で整理しよう
新しい資格を検討する時、私は必ずこの「3つの質問」を自分に投げかけるようにしています。
📝 資格検討チェックリスト
✅ この資格は、私の本当にやりたいことに直結してる?
✅ 今の私に本当に必要なタイミング?
✅ 取得後、具体的にどう活用するかイメージできる?
実例:私の場合 心理カウンセラーの資格を検討した時:
- やりたいこと:患者さんの心のケアをもっと上手にしたい ✅
- 必要性:今すぐ?それとも看護師としてもう少し経験を積んでから? ⚠️
- 活用法:病院でのカウンセリング?開業?具体的なイメージは… ❓
結果的に「今は看護師としての基礎をもっと固めよう」と判断し、心理学は書籍や研修で学ぶことにしました。おかげで焦らず、自分のペースで学べています😊

⏰ 方法2:「一点集中タイム」で学習効率アップ!
複数分野を同時に学ぶのではなく、3〜6ヶ月単位で一つの分野に集中する期間を作ってみてください。
🗓️ 私の「一点集中」スケジュール例:
| 期間 | 集中分野 | 具体的な取り組み |
|---|---|---|
| 1〜3月 | 心理学 | 基礎心理学の書籍3冊 |
| 4〜6月 | 英語学習 | 医療英語検定対策 |
| 7〜9月 | 看護研究 | 論文執筆・学会発表準備 |
この方法に変えてから、一つひとつの学習がより深く身についている実感があります。そして何より、「今日は何を勉強しよう?」「あれもこれもやらなくちゃ」という迷いがなくなって、勉強へのハードルがぐんと下がりました✨
🎈 方法3:「70%の完璧」で心をラクにしよう
完璧主義の私たちは、ついつい「100%理解するまで次に進めない」と思いがちです。でも実際の現場では、70%の理解でも十分役に立つことが多いんです。
💡 70%理解の威力:実体験から
保育実習で初めて2歳児クラスを担当した時のこと。発達心理学の知識は教科書レベルでしたが、「2歳は自我が芽生える時期」という基本を知っているだけで、子どもたちのイヤイヤに適切に対応できました。
完璧な知識よりも、「相手を思いやる気持ち」や「学び続ける姿勢」の方が、現場では圧倒的に重要だったりします。
🌟 まとめ:あなたらしい学びの道を歩もう
✅ 今日のポイント振り返り
- 🎯 目的を明確にする: なぜその資格が欲しいのか3つの視点でチェック
- ⏰ 一点集中: 3〜6ヶ月単位で一つずつ、深く学ぶ
- 🎈 70%でOK: 完璧を求めすぎず、実践で活かせるレベルを目指す
- 💝 内なる声: 周囲の期待より、自分の本当の興味を大切に
- 🌱 学びは一生: 今すぐ全てを習得する必要はない
💫 一番大切なのは「自分らしい成長」です
資格はあくまで「手段」であって「目的」ではありません。あなたのペースで、あなたらしい学びの道を歩んでいくことが、結果的に最も豊かな人生につながります。
完璧主義の重荷を少しだけ手放して、今日から「楽しい学び」を始めてみませんか?✨
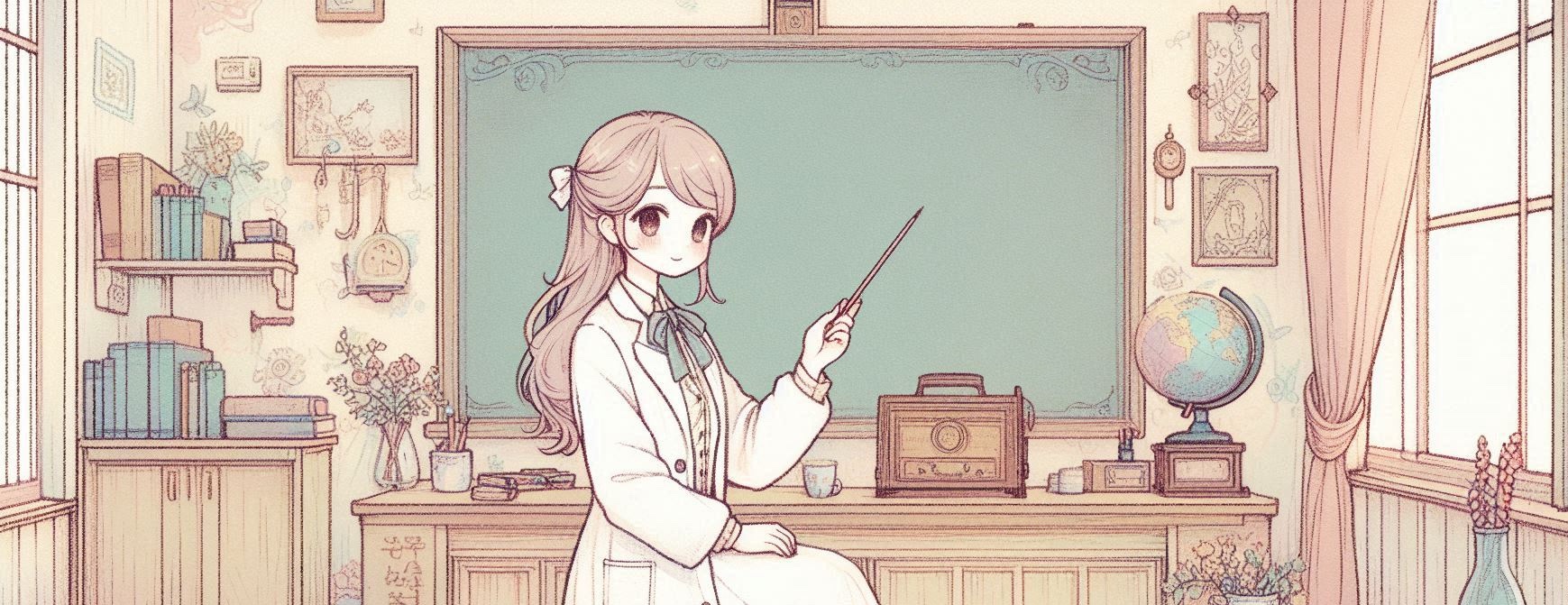
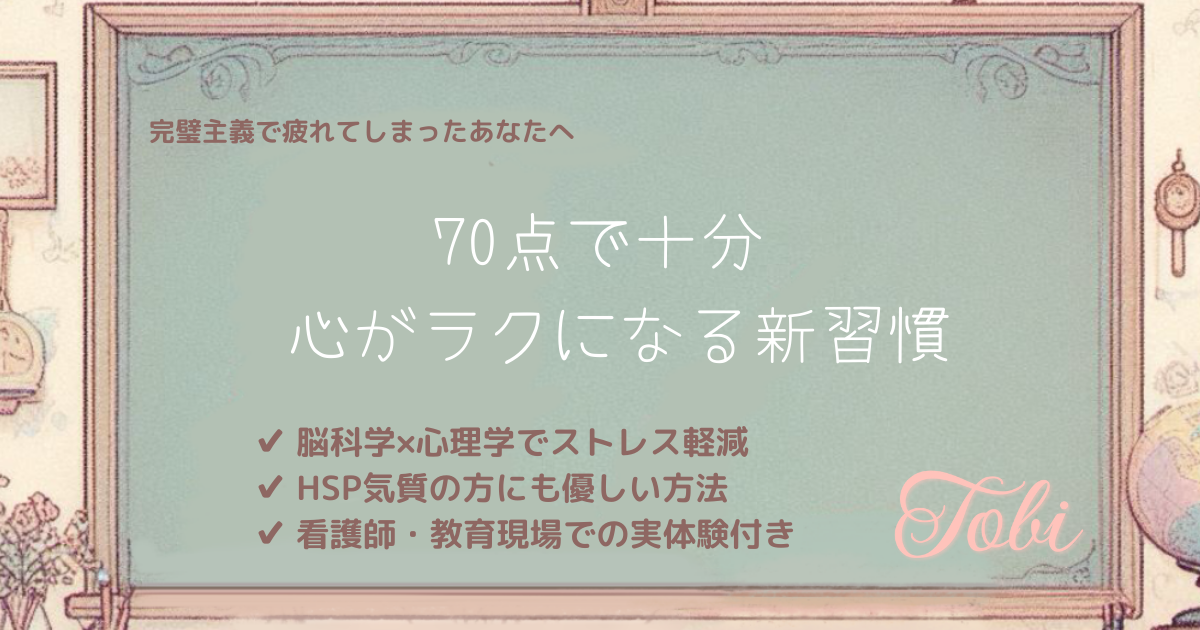
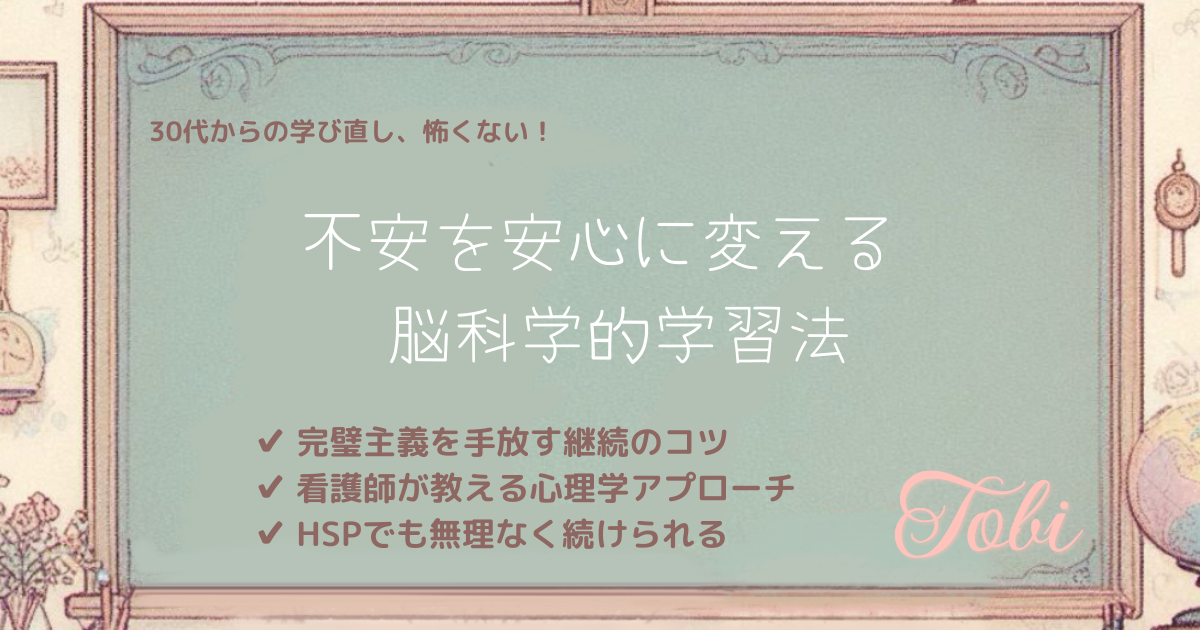
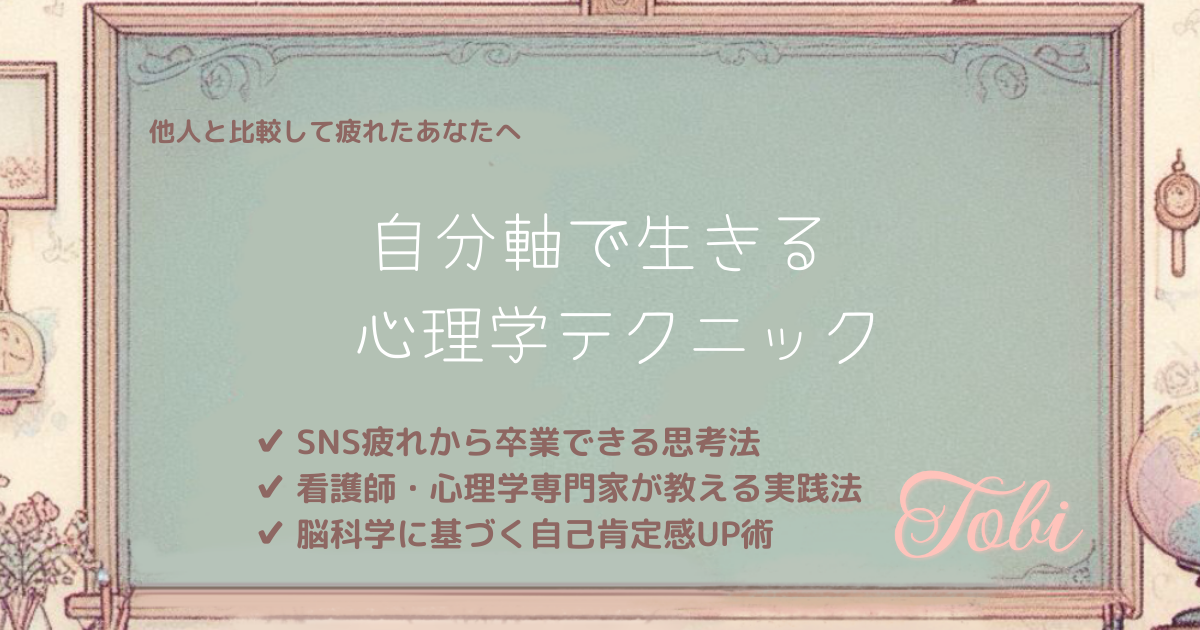

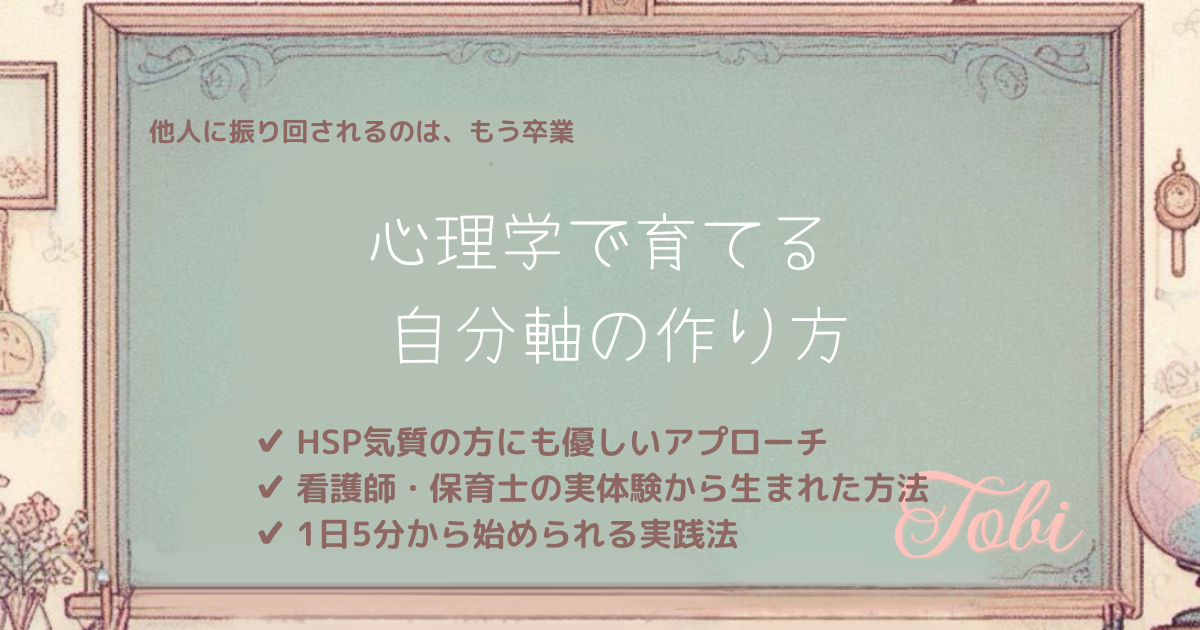
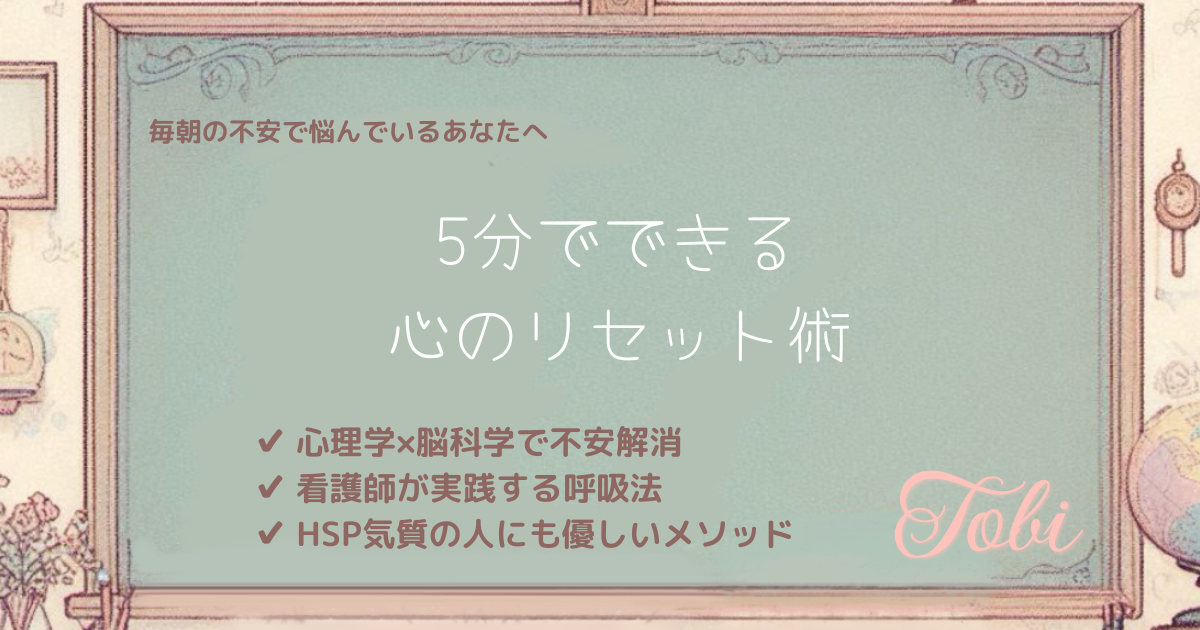


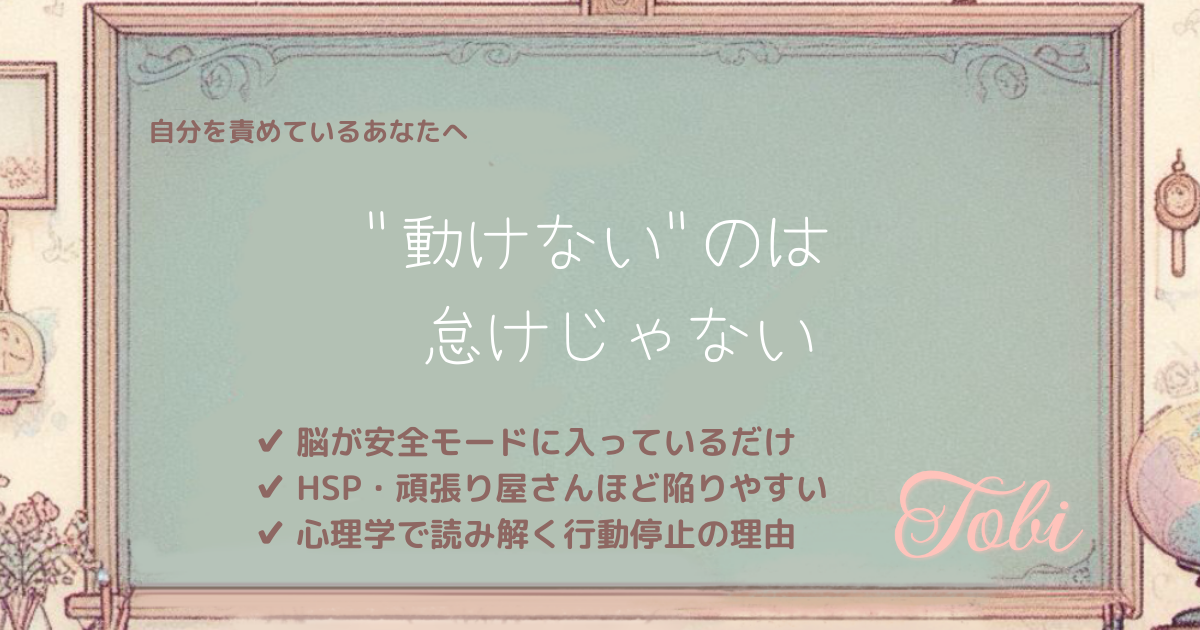
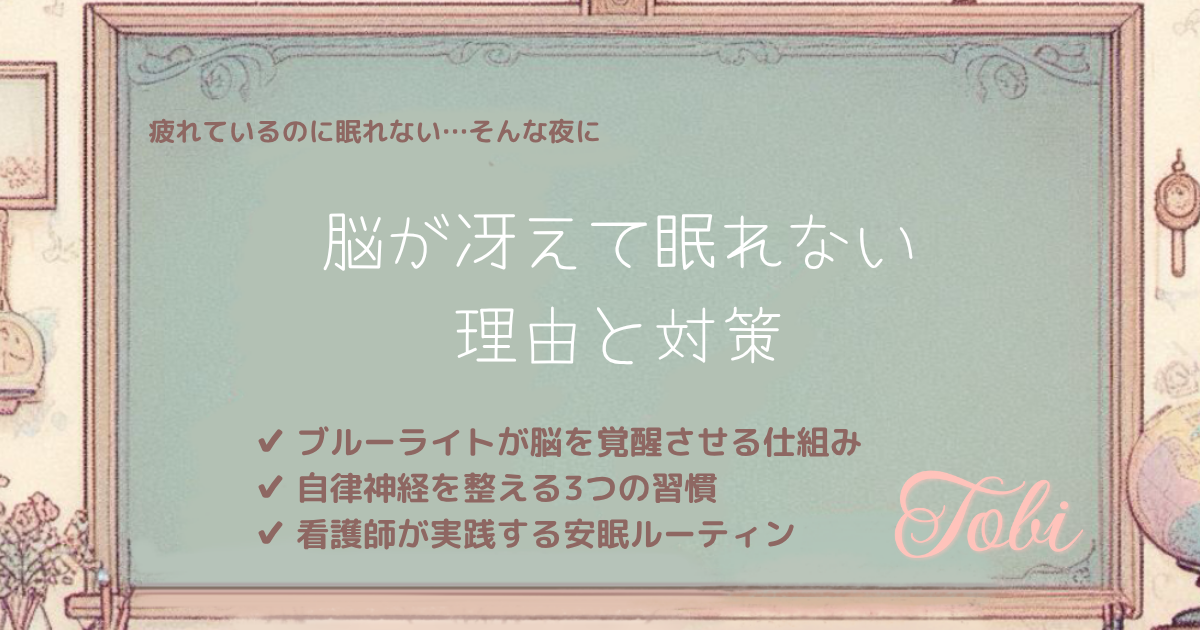
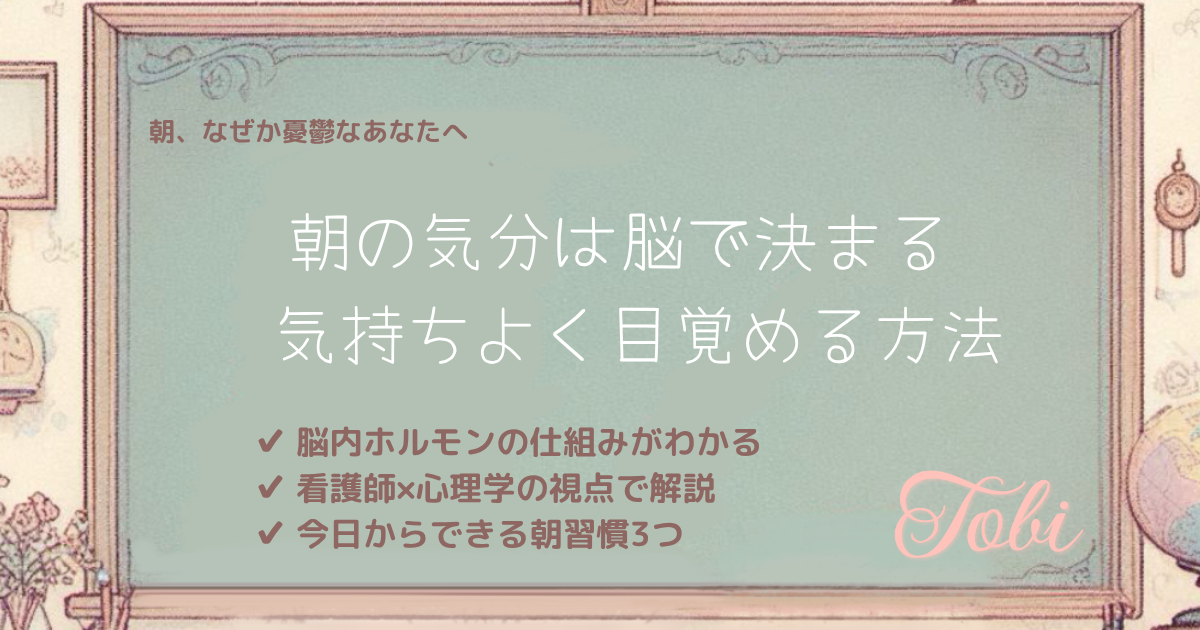
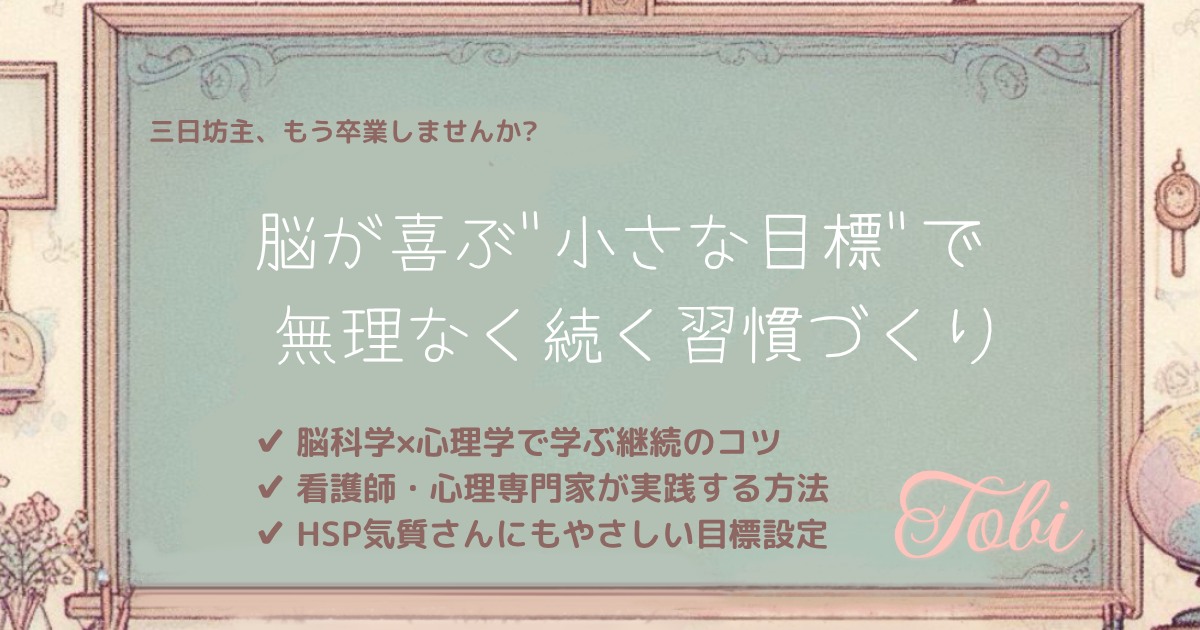
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません