😮💨 「疲れた…」の正体、実は2種類あるって知ってた?

「最近なんだか頭が働かない…」
「ちゃんと寝てるのに、スッキリしない…」
こんな風に感じること、ありませんか?
実は私も、看護師として夜勤をしていた頃、休日に10時間寝ても全然回復しないという謎の状態に悩まされていました。
体は元気。でも頭がぼんやり。
かと思えば、別の日は頭は冴えているのに、なぜか涙が出そうになる…。
「私、どうしちゃったんだろう?」
そんな風に自分を責めていた時期もあります。
でもある時、気づいたんです。
疲れには「脳疲労」と「心の疲れ」という2種類があって、それぞれ回復法が全く違うということに。
今日は、看護師・心理学の視点から、この2つの疲れの違いと、あなたに合った回復法をお伝えしますね✨
目次
💡 結論:疲れの種類を知れば、回復法が変わる!
【この記事で分かること】
✅ 脳疲労=情報処理のオーバーワークで脳が疲れている状態
✅ 心の疲れ=感情が積み重なって心が疲弊している状態
✅ それぞれに合った科学的な回復法
この2つは疲れの「場所」も「原因」も違うので、回復方法もまったく異なります。
「休んでいるのに疲れが取れない…」
その理由は、もしかしたら疲れの種類に合っていない休み方をしているからかもしれません。
まずは自分の疲れがどちらなのかを知ることが、スッキリ回復への第一歩ですよ🌱
🧠 脳疲労と心の疲れ、どう違うの?
📱 脳疲労=「頭のメモリ不足」状態
脳疲労とは、脳の情報処理機能が一時的に低下している状態のこと。
スマホやパソコンで大量の情報を処理したり、「あれもこれも」とマルチタスクを続けることで、脳の前頭前野(思考や判断を司る部分)がオーバーヒートしてしまうんです。
🖥️ たとえるなら…
パソコンでたくさんのアプリを開きすぎて、フリーズしている状態。「メモリ不足」で動作が重くなっている感じです。
こんな症状、ありませんか?
- 📖 本を読んでも内容が頭に入ってこない
- 🤔 簡単な決断ができない(昼ごはん何にしよう…がすごく悩む)
- 📝 さっき言われたことを忘れる
- ⏰ 時間の感覚がおかしくなる
- 😑 好きなことすら楽しめない(でも気持ちは元気)
私が保育園で働いていた時、20人の子どもの様子を同時に見ながら、保護者対応して、書類も書いて…という日々を送っていたら、帰りの電車で本を読んでも内容が入らず、ページを眺めるだけになっていたということがよくありました😅
これ、まさに脳疲労のサインだったんですね。
💡 脳科学メモ
前頭前野は「脳の司令塔」。情報処理、意思決定、感情コントロールなど、高度な認知機能を担っています。現代人は1日に約3万5000回の決断をしていると言われ、脳は常にフル稼働状態なんです。
💔 心の疲れ=「心のバッテリー切れ」状態
一方、心の疲れは、感情の処理が追いつかず、心理的なエネルギーが枯渇している状態。
人間関係のストレス、不安、悲しみ、怒り、我慢…こうしたネガティブな感情が積み重なることで生じます。
📱 たとえるなら…
スマホのバッテリー残量が1%で、いつ電源が切れてもおかしくない状態。充電しないと動けません。
こんな症状、ありませんか?
- 😢 些細なことで涙が出そうになる
- 😔 何もやる気が起きない
- 🙅 人と会いたくない、話したくない
- 💤 寝ても寝ても眠い
- 😞 「自分はダメだ」と自己否定が強くなる
看護師時代、患者さんが急変した日の夜。
処置は冷静にできた。頭も働いた。
でも帰宅した途端、涙が止まらなくなったことがありました。
「何で泣いてるんだろう、私…」
当時は理解できなかったけれど、今思えば、患者さんへの不安や自責の念が、心に溜まっていたんですね。
💗 心理学メモ
感情は「エネルギー」です。喜びも悲しみも、すべて心のエネルギーを使います。特にネガティブな感情は処理に大きなエネルギーを消費するため、溜め込むと心が枯渇してしまうんです。
🤔 なぜ2つを混同しちゃうの?
この2つが混同されやすい理由。それは「同時に起こることが多いから」です。
たとえば、こんなシーン、覚えがありませんか?
📧 朝からメールが100通(脳疲労)
→ 上司に理不尽なことを言われる(心の疲れ)
→ 会議資料を作りながらチャット対応(脳疲労)
→ 同僚の愚痴を聞く(心の疲れ)
現代社会では、情報処理と感情労働が同時進行することがほとんど。
だから「疲れた」と感じた時、どっちの疲れが強いのか分からなくなるんです。
私自身、養護教諭として働いていた時は、
- 保健室に来る子どもの話を聞きながら(心の疲れ)
- 同時に他の子のケガの様子を確認して(脳疲労)
- 保護者への連絡文を考えて(脳疲労)
- 先生方の相談にも応じて(心の疲れ)
…と、脳と心が同時にフル稼働していました😅
だからこそ。
「自分は今、どっちの疲れが強いのか?」
これを見極めることが、効果的な回復への第一歩なんです✨
✨ それぞれの疲れに合った回復法とは?
さて、ここからが本題。
それぞれの疲れに、どう対処すればいいのでしょうか?
🧠 脳疲労の回復法:「情報断ち」でリセット
脳疲労には「情報を減らす休息」が効果的です。
私が実践している方法:
① スマホを別の部屋に置く(10分間)
→ 窓の外を眺める、空を見る、ぼーっとする
→ 「何も考えない時間」が脳のメモリをリセットしてくれます
② 単純作業をする
→ 皿洗い、掃除、洗濯物をたたむ
→ 五感を使って「今ここ」に集中すると、脳が休まります
③ 散歩(できれば緑のある場所)
→ 歩くリズムが脳をリラックスさせます
→ 緑を見ると、前頭前野の活動が落ち着くという研究も
④ デジタルデトックス
→ 寝る1時間前はスマホを見ない
→ 休日の午前中だけでも「情報ゼロ時間」を作る
🌿 看護師の視点から
病院の患者さんも、検査や治療の合間に「窓の外を眺める時間」を大切にしています。何もしない時間は、回復のために必要な時間なんです。
💗 心の疲れの回復法:「感情を吐き出す」ことが鍵
心の疲れには「感情の吐き出し」が必要です。
私が実践している方法:
① 「誰にも見せないノート」に書き殴る
→ 今日のモヤモヤ、怒り、悲しみ…全部書く
→ 書くだけで、不思議と心が軽くなります
→ 私は100均のノートを使ってます😊
② 信頼できる人に話す
→ アドバイスは要らない。ただ聞いてもらうだけでOK
→ 「そうだったんだね」と共感してもらえるだけで救われます
③ 泣ける映画や音楽で涙を流す
→ 涙にはストレスホルモンを排出する効果があります
→ 我慢せず、思いっきり泣くことも大切
④ 自分を労わる時間を作る
→ 好きなお茶を丁寧に入れる
→ お風呂にゆっくり浸かる
→ 「今日もよく頑張ったね」と自分に声をかける
💗 心理学の視点から
感情は「表現する」ことで初めて処理されます。溜め込むと、心のコップから溢れてしまう。だから、少しずつ外に出すことが大切なんです。
⚖️ バランスが大事:両方やってみる
実際には、両方の疲れが同時に来ていることが多いです。
そんな時は、
→ まず脳疲労のケア(情報を減らす)
→ 次に心の疲れのケア(感情を吐き出す)
この順番がおすすめ。
脳が疲れていると、感情の整理もうまくできないので、まずは脳を休ませてあげることが先決です🌱
🌸 まとめ:疲れの正体を知って、自分に優しく
今日のポイントをおさらいしますね✨
📌 この記事のまとめ
✅ 脳疲労=情報処理のオーバーワーク → 症状:集中できない、物忘れ、決断できない
✅ 心の疲れ=感情の蓄積と枯渇 → 症状:やる気が出ない、涙が出る、人と会いたくない
✅ 脳疲労の回復法=情報を減らす(スマホ断ち、散歩、単純作業)
✅ 心の疲れの回復法=感情を吐き出す(書く、話す、泣く)
✅ 両方が同時に来ている時は、まず脳疲労から対処
🌟 一番伝えたいこと 🌟
「疲れにも種類がある」
自分の疲れの正体が分かれば、
「休んでいるのに回復しない」という悩みから抜け出せます。
あなたの今の疲れは、脳ですか? それとも心ですか?
まずはそこに気づいてあげることが、回復への第一歩。
「ちゃんと休めない自分はダメだ」なんて思わないでくださいね。
疲れの種類に合った休み方を知らなかっただけ。
あなたのペースで、少しずつ整えていきましょう🌱
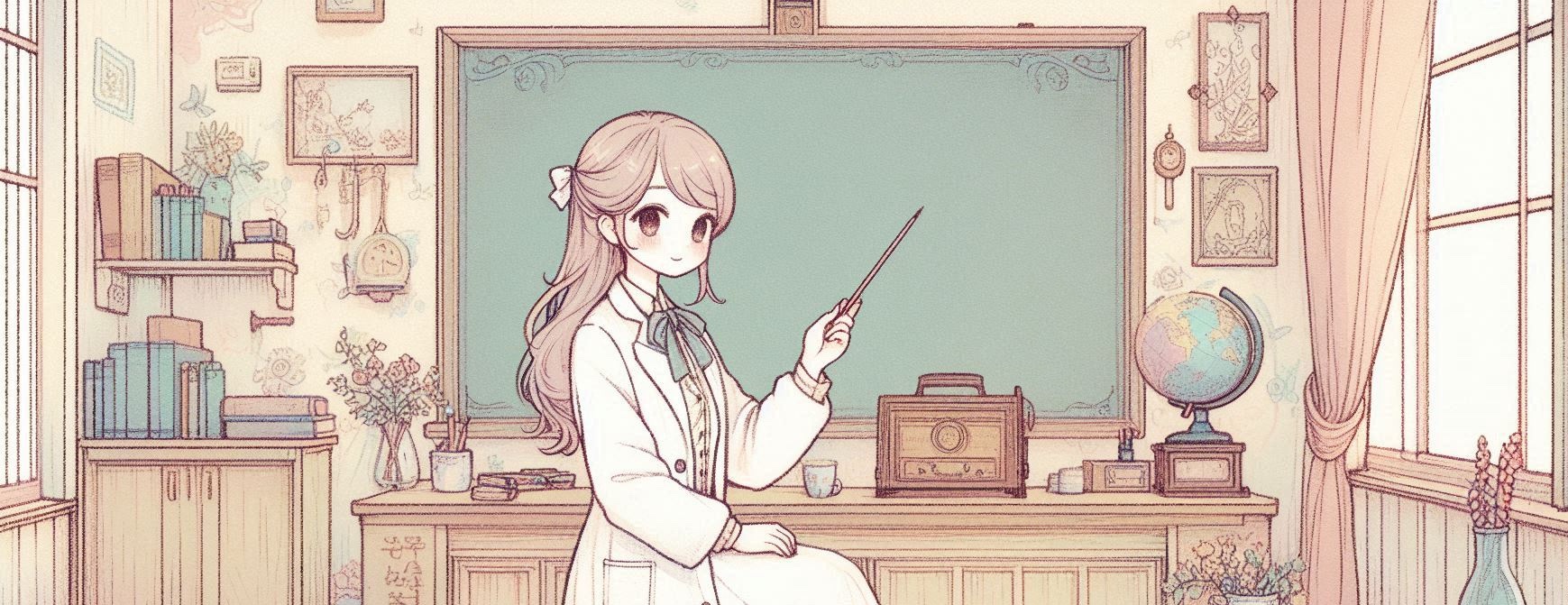
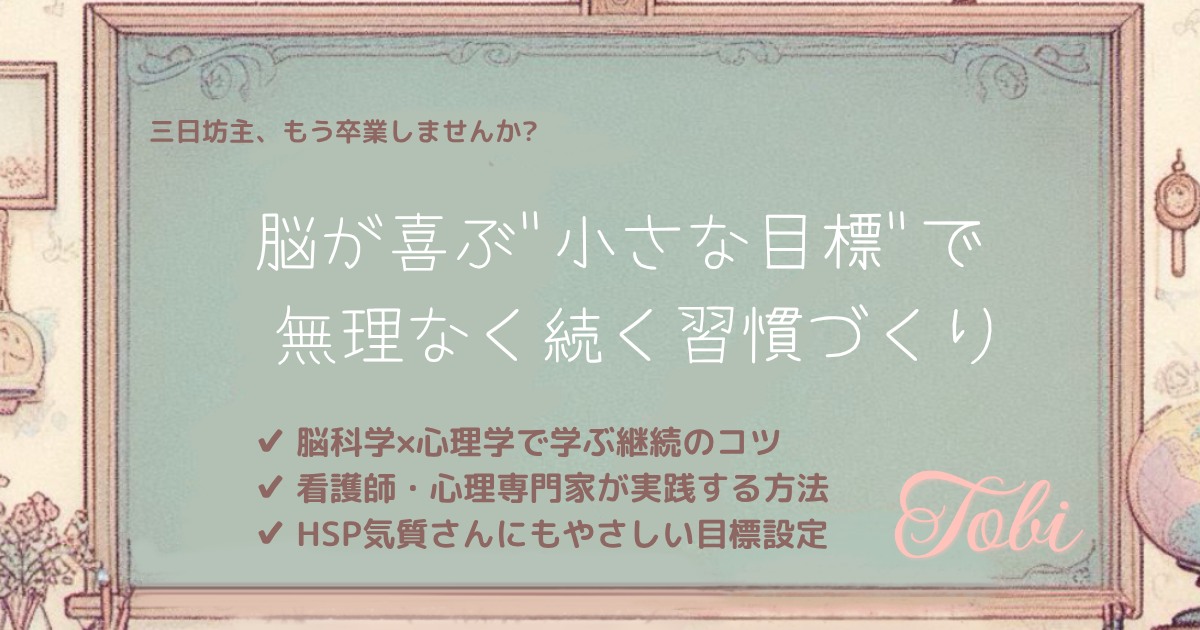
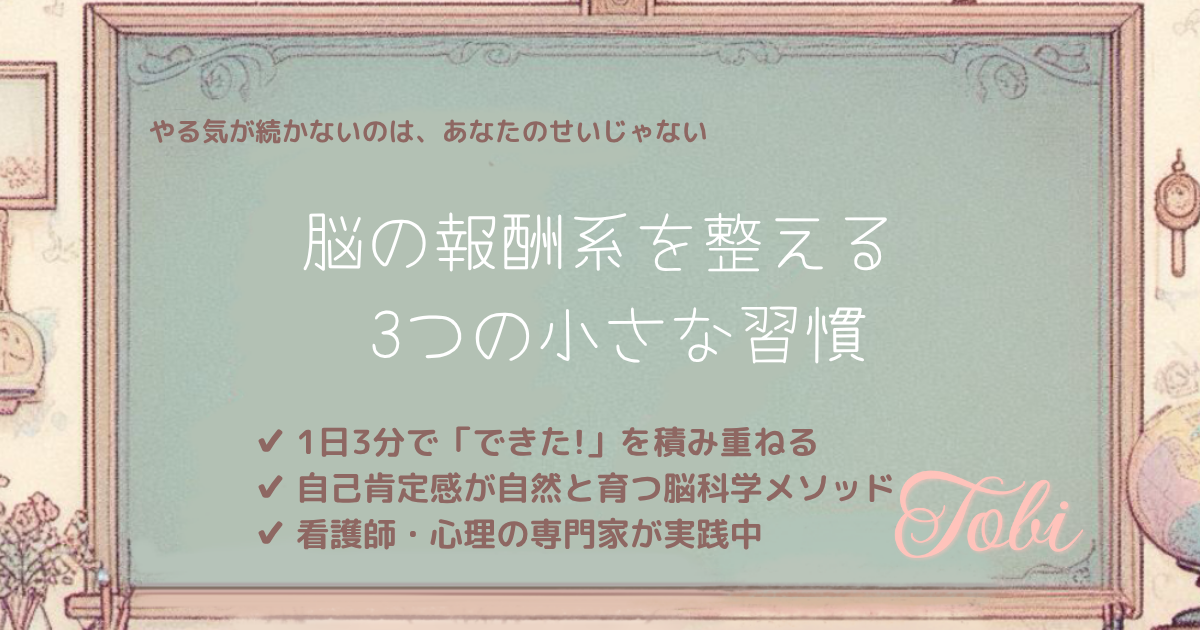
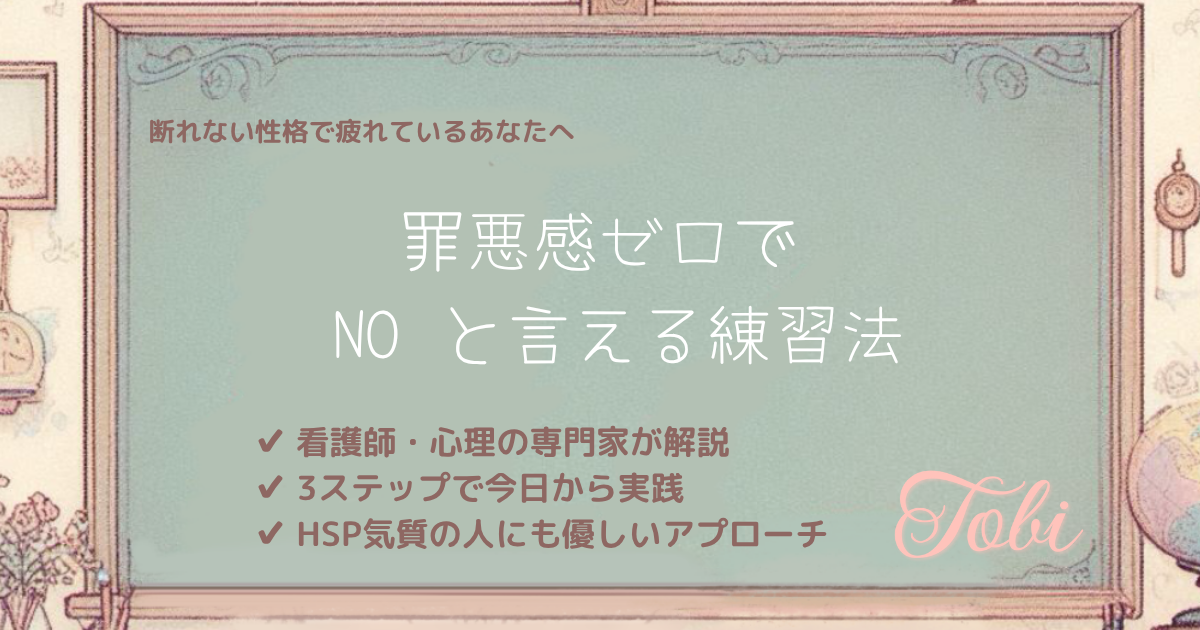



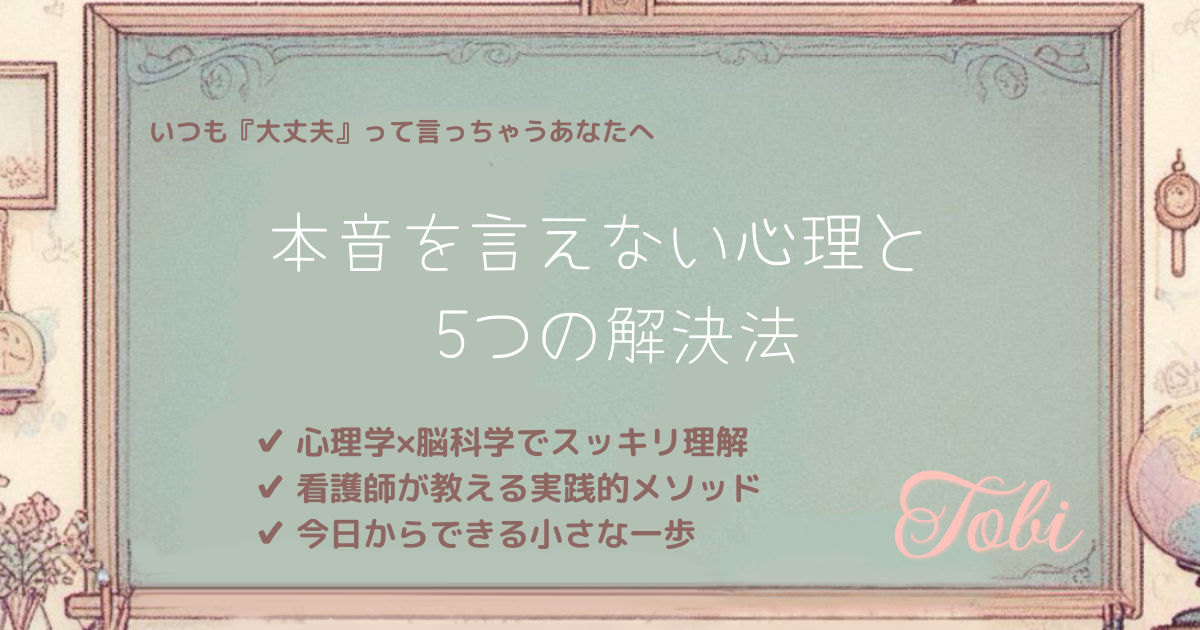

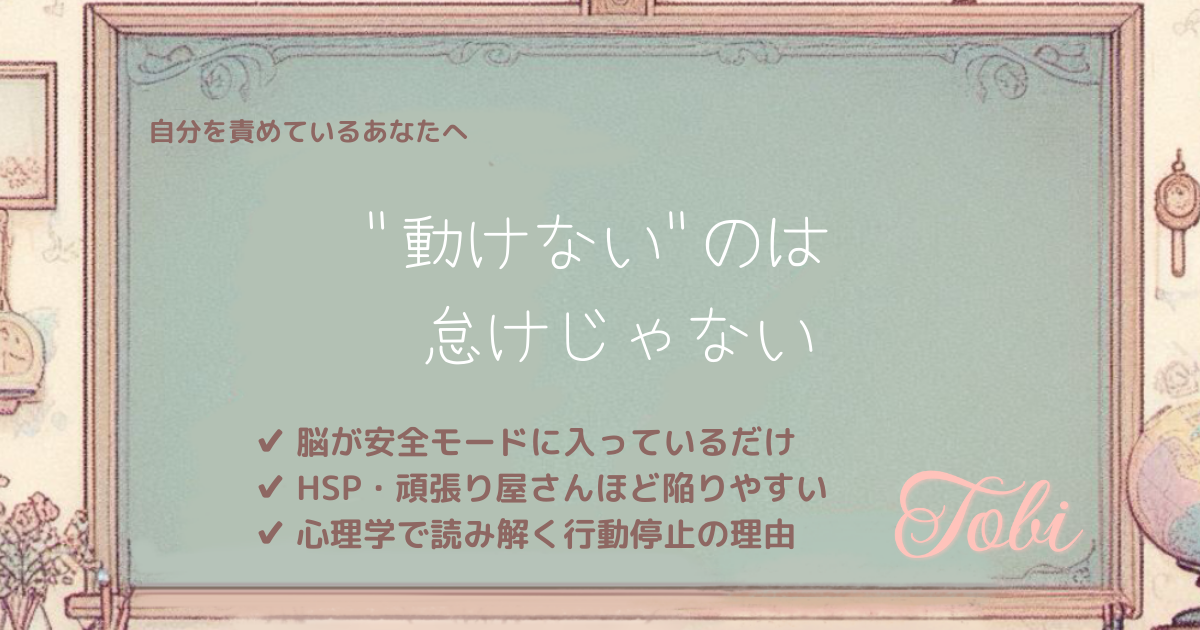

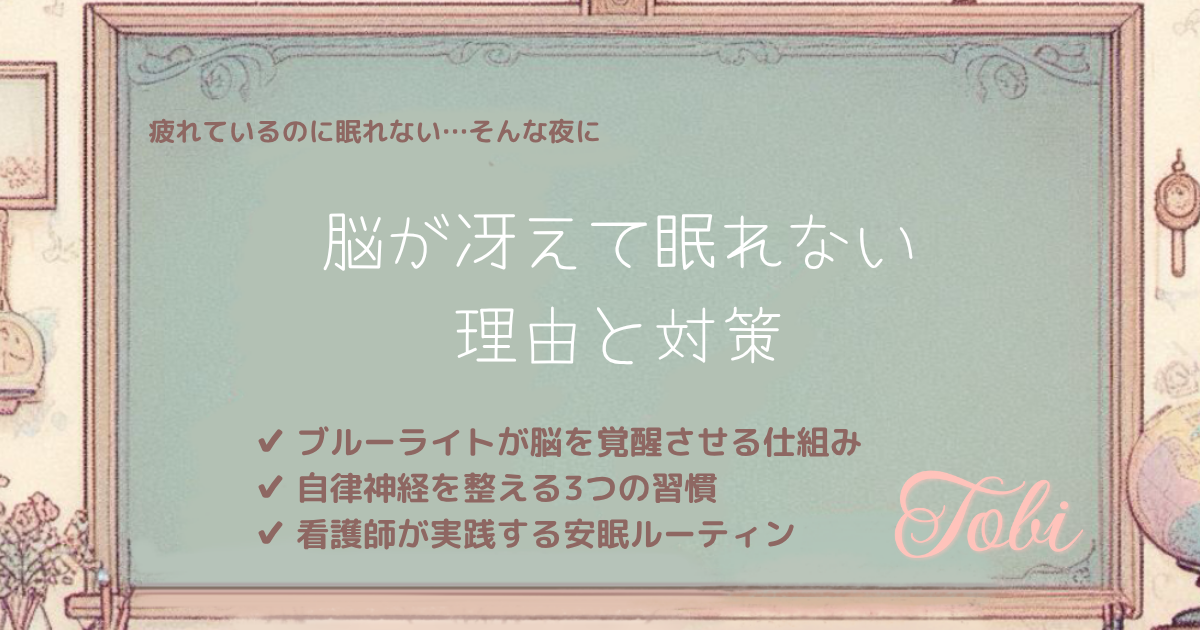
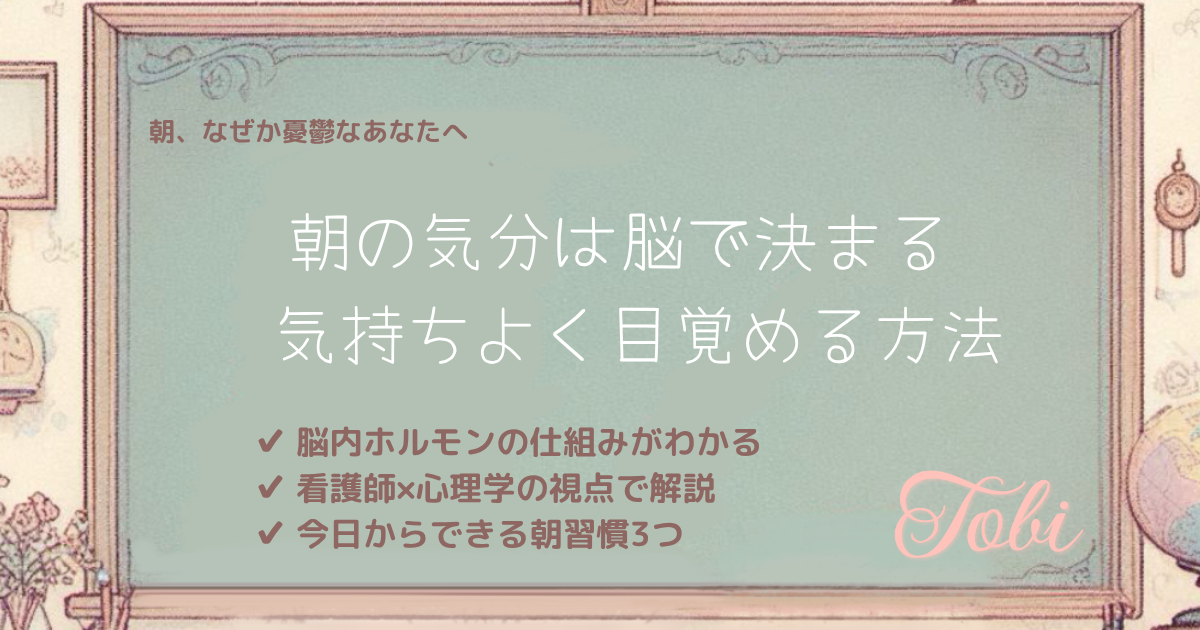
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません