「今年こそは!」が続かないのは、あなたのせいじゃない

「今年こそ資格を取る!」「毎日30分勉強する!」
年明けや新年度に、こんな目標を立てたこと、ありませんか?
でも気づけば3日後には元通り。「またできなかった…私って意志が弱いのかな」って自分を責めてしまう。
実は、これ、あなたの意志の問題じゃないんです。
看護師として働きながら資格試験の勉強をしていた頃、私も「参考書を1ヶ月で1冊終わらせる!」と意気込んでは、3日目で挫折…ということを何度も繰り返してきました。夜勤明けで疲れているのに「やらなきゃ」と自分を追い込んで、結局できずに自己嫌悪。
でも、目標の”立て方”を変えただけで、不思議なほどスムーズに続けられるようになったんです。
今日は、脳科学と心理学の視点から、「続けられる目標設定のコツ」をお伝えしますね。
目次
結論:目標は「バカバカしいくらい小さく」が正解
目標設定のコツは、「脳が安心できるくらい小さな目標」にすること。
「え、そんなんで意味あるの?」って思いますよね。でもこれ、脳科学的に理にかなった方法なんです。
大きな目標を掲げると、脳は「これは達成できない=危険」と判断して、防衛反応でやる気を失います。
逆に「これならできそう」と思える小さな目標は、脳にとって”安全な挑戦”。ドーパミン(やる気ホルモン)が出やすく、自然と行動が続くようになるんです。
なぜ「高すぎる目標」は挫折しやすいの?脳の仕組みを知ろう
💡 脳は「変化」が苦手な臓器
私たちの脳には、「生存を最優先する」という本能があります。
大きな変化や高いハードルは「危険」と判断されて、扁桃体(へんとうたい=感情の中枢)が「やめておこう」というブレーキをかけちゃうんです。
たとえば、こんな目標。
- 「毎日1時間勉強する!」
- 「週5日ジムに通う!」
- 「1ヶ月で参考書を1冊終わらせる!」
一見、素晴らしい目標ですよね。でも脳にとっては「いつもと違う大きな変化=脅威」なんです。
すると脳は本能的に、元の安全な状態(=何もしない状態)に戻そうとします。これが「三日坊主」の正体。
🧠 脳の中で何が起こっているの?
| 脳の部位 | 役割 | 高い目標への反応 |
| 扁桃体 | 感情・危険察知 | 「これは無理!危険!」→ストレス |
| 前頭前野 | 計画・実行 | 「どうすれば…」→思考停止 |
| 線条体 | 報酬・やる気 | 「達成できない」→ドーパミン出ない |
看護師時代、患者さんに「明日から毎日30分歩いてくださいね」とお伝えすると、多くの方が続けられませんでした。
でも「玄関まで歩いてみましょうか」「まず5分だけ」と小さなステップにすると、「それならできそう」と表情が明るくなるんです。
✨ 脳が喜ぶ「小さな目標」の威力
一方、「参考書を1ページだけ読む」「問題を1問だけ解く」といった小さな目標は、脳にとって”安全圏内の挑戦”。
- ✅ 扁桃体が警戒しない → ストレスが少ない
- ✅ 前頭前野が働きやすい → 行動しやすい
- ✅ 達成感が得られる → ドーパミンが出て、また続けたくなる
保育士として働いていたとき、子どもに「全部片付けて!」と言うより、「この積み木だけ箱に入れようか」と声をかけると、スムーズに動き出すことに気づきました。
大人の脳も同じ。”小さくする”ことが、行動のスイッチを入れるんです。
💭 HSP気質さんには特に効果的
繊細で真面目なHSP(Highly Sensitive Person)さんは、「完璧にやらなきゃ」「ちゃんとやらなきゃ」と自分を追い込みがち。
でも、脳は”完璧主義”が苦手なんです。高すぎる目標はプレッシャーとなり、かえって動けなくなります。
私自身、HSS型HSP(刺激追求型のHSP)で、「あれもこれもやりたい!」という気持ちと「でもできない…」というギャップに苦しんできました。
でも、目標を“バカバカしいくらい小さく”してみたら、不思議と続けられるように。「これくらいならできそう」という安心感が、脳のストレスを下げてくれたんです。
📚 関連書籍のご紹介
目標設定や習慣化についてもっと深く知りたい方は、こちらの書籍もおすすめです!
今日からできる!「やさしい目標設定」3ステップ
では、具体的にどうやって目標を立てればいいのか。私が実践して効果があった方法を3ステップでご紹介しますね。
ステップ① 理想の目標を”10分の1″にしてみる
まずは、立てた目標を思い切り小さくします。
「毎日30分勉強」→「毎日3分勉強」
「参考書1章読む」→「参考書1ページ読む」
「問題集10問解く」→「問題集1問解く」
「え、それじゃ意味ないでしょ?」って思いますよね。
でもまずは「続ける」ことが最優先。1問でも毎日続ければ、1ヶ月で30問。続けないゼロよりずっと進んでいます。
私の実例をお話しすると、「参考書を開くだけでOK」という目標から始めました。本当に、開くだけ。読まなくてもいい、という超低ハードル。
すると不思議なことに、開いたついでに「ちょっと読んでみようかな」と自然に行動が広がっていったんです。
ステップ② 「やらない日があってもOK」と決める
完璧を目指さないことも大切。
「週3日できたら合格」「月10日できたら花マル」くらいの余裕を持ちましょう。
脳は”逃げ道”があると安心します。「絶対毎日!」というプレッシャーがなくなると、かえって続けやすくなるんです。
夜勤や残業で疲れた日、体調が悪い日は、無理しなくていい。それを自分に許可してあげてください。
ステップ③ 達成したら「小さくほめる」
「たった3分でしょ」「1問だけじゃん」って思わないで。
「今日もできた!」「続いてる!」と自分を認めてあげてください。
この小さな達成感の積み重ねが、脳に”続けたい”と思わせます。ドーパミンが出て、次の行動につながるんです。
私は手帳に「✓」をつけるだけでも、ちょっと嬉しくなります。シールを貼るのもおすすめ。視覚的に「続いてる!」が見えると、モチベーションが上がりますよ。
📝 習慣化をサポートするアイテム
小さな達成感を見える化するのに、こんなアイテムもおすすめです
よくある質問:「小さすぎて意味ない」と感じたら?
Q. 1問だけじゃ、目標達成に遠すぎませんか?
A. 「0」と「1」では天と地ほどの差があります。
続けないゼロより、1問でも続ける方が圧倒的に前進しています。そして、続けているうちに自然と「もうちょっとやろうかな」という気持ちが生まれてくるんです。
Q. やる気がある日はもっとやってもいいですか?
A. もちろんOK!でも「毎日それをやらなきゃ」とは思わないで。
調子がいい日は10問解いてもいいし、疲れた日は1問でいい。「最低ライン」を守ることが大切です。
まとめ:「小さな一歩」が、未来を変える
今日のポイントをおさらいしますね。
- ✅ 高い目標は脳が「危険」と判断して、やる気が続かない
- ✅ 小さな目標は脳が安心して、ドーパミンが出やすい
- ✅ 「バカバカしいくらい小さく」が継続の秘訣
- ✅ 完璧を目指さず、「できた日」を積み重ねる
- ✅ 小さな達成感が、次の行動を生む
一番大切なのは、「これならできそう」と脳が安心できる目標を作ること。
「こんな小さな目標でいいのかな?」って不安になったら、それは”ちょうどいいサイズ”のサイン。
あなたのペースで、あなたに合った”小さな一歩”を見つけてくださいね。
1日1ページでも、1ヶ月で30ページ。半年で180ページ。気づいたら参考書1冊終わってます。
小さな一歩の積み重ねが、未来を変える。
あなたの挑戦を、心から応援しています!
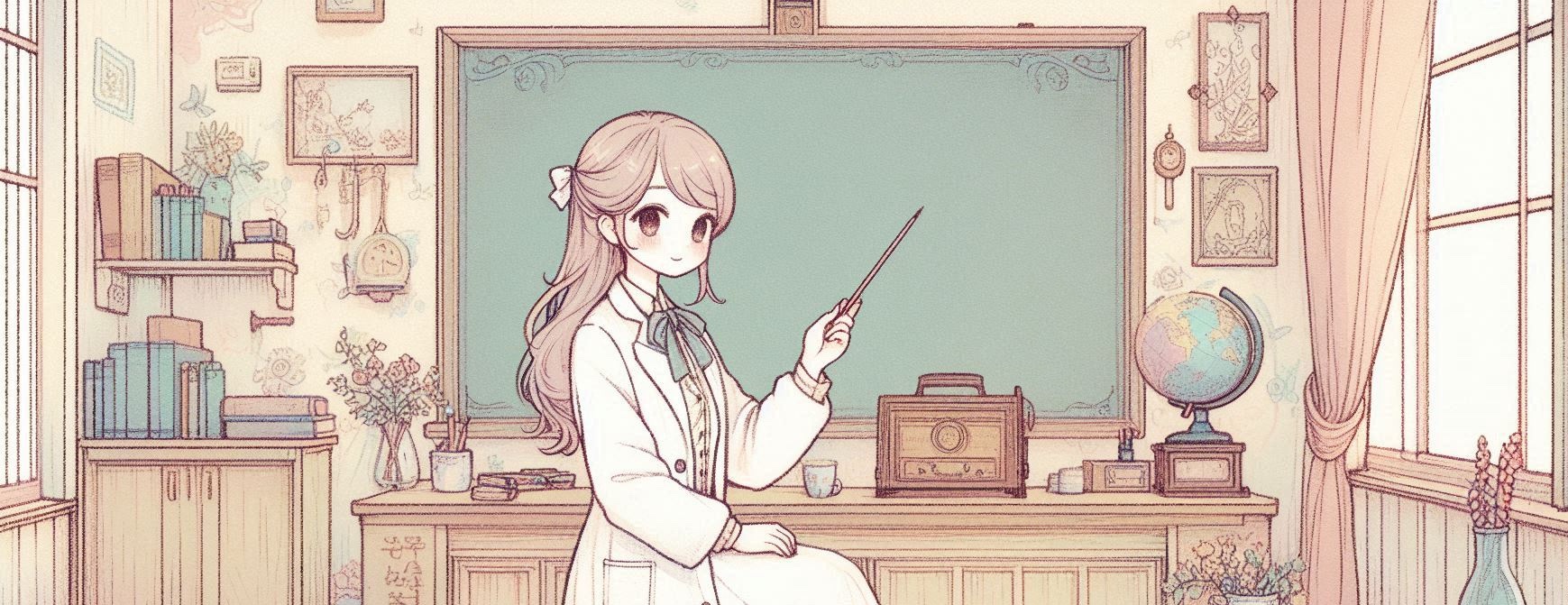
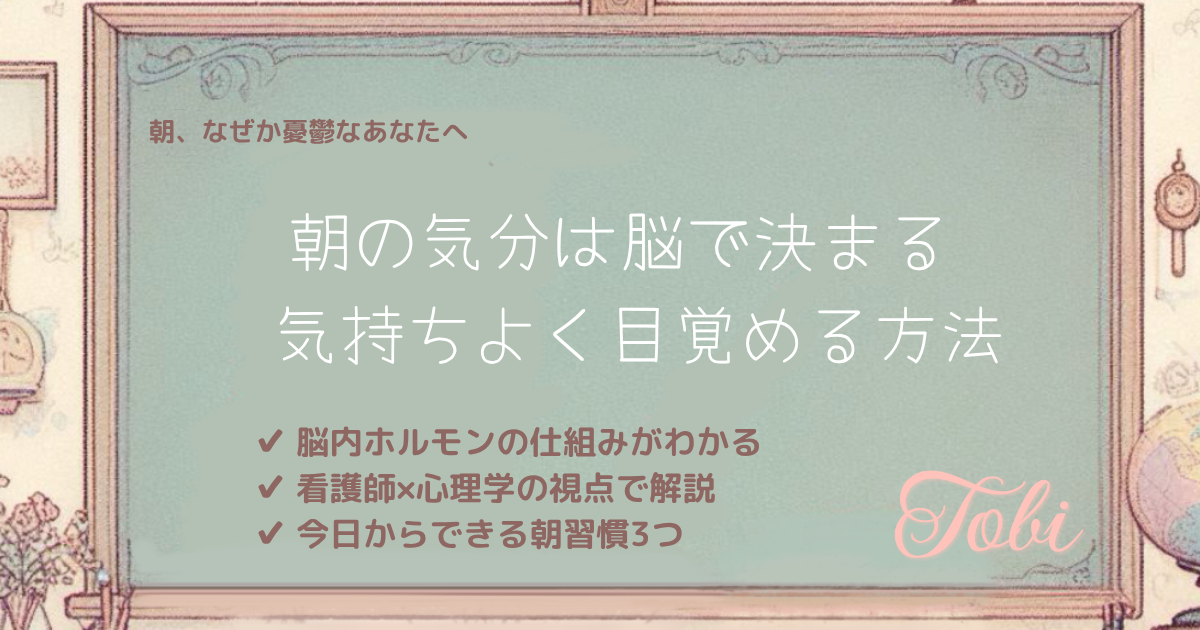
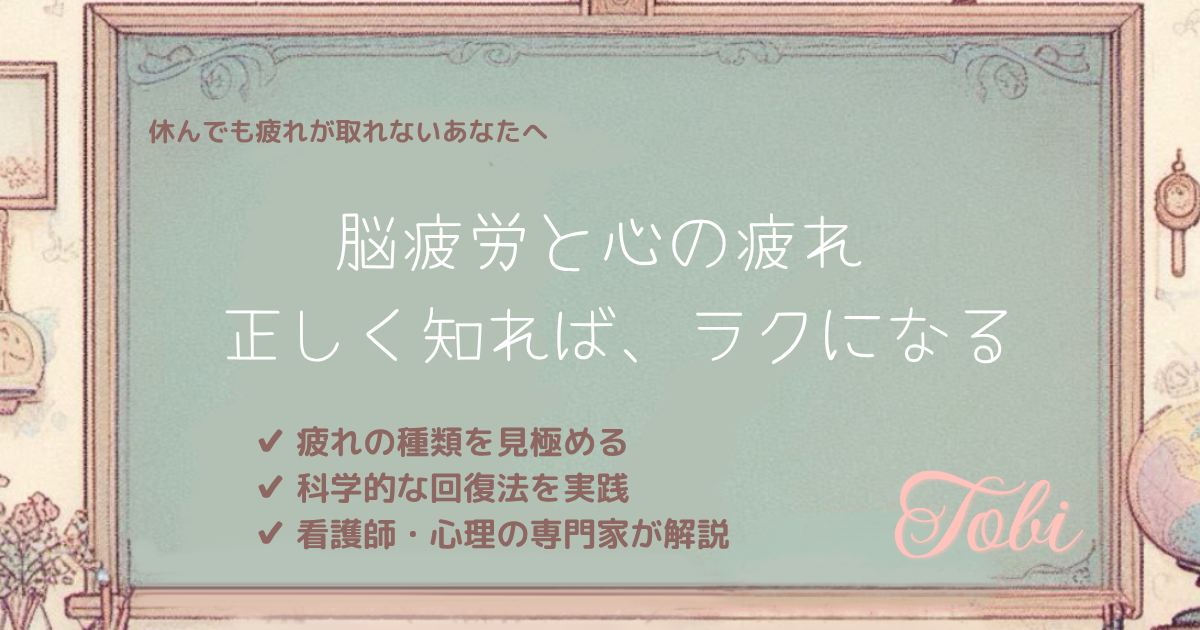

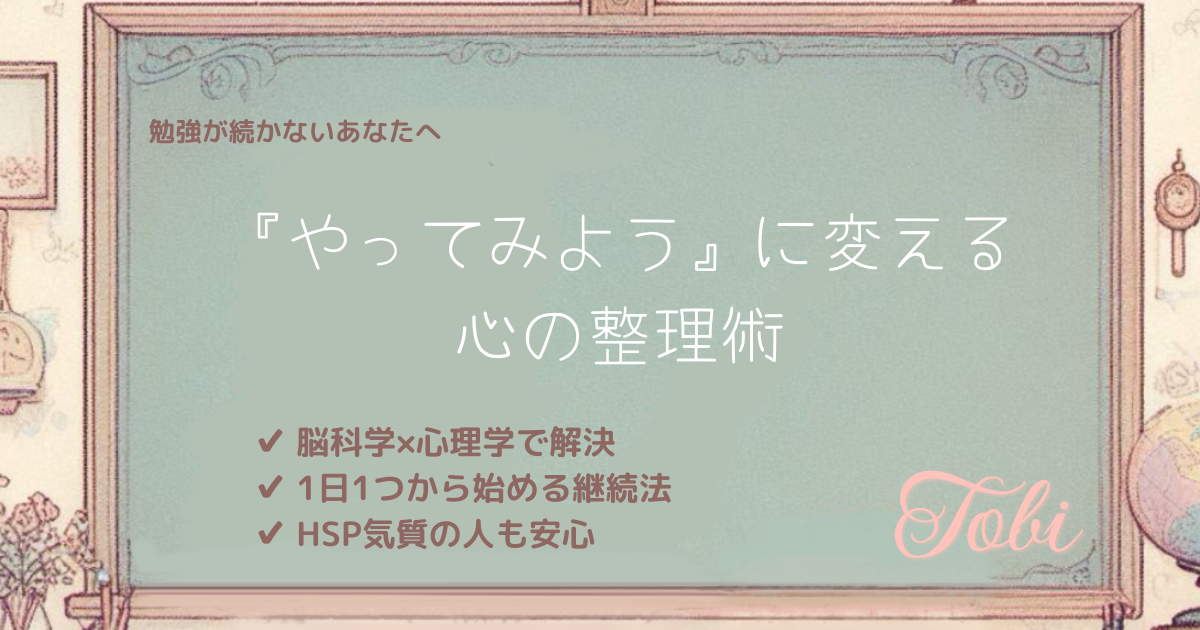
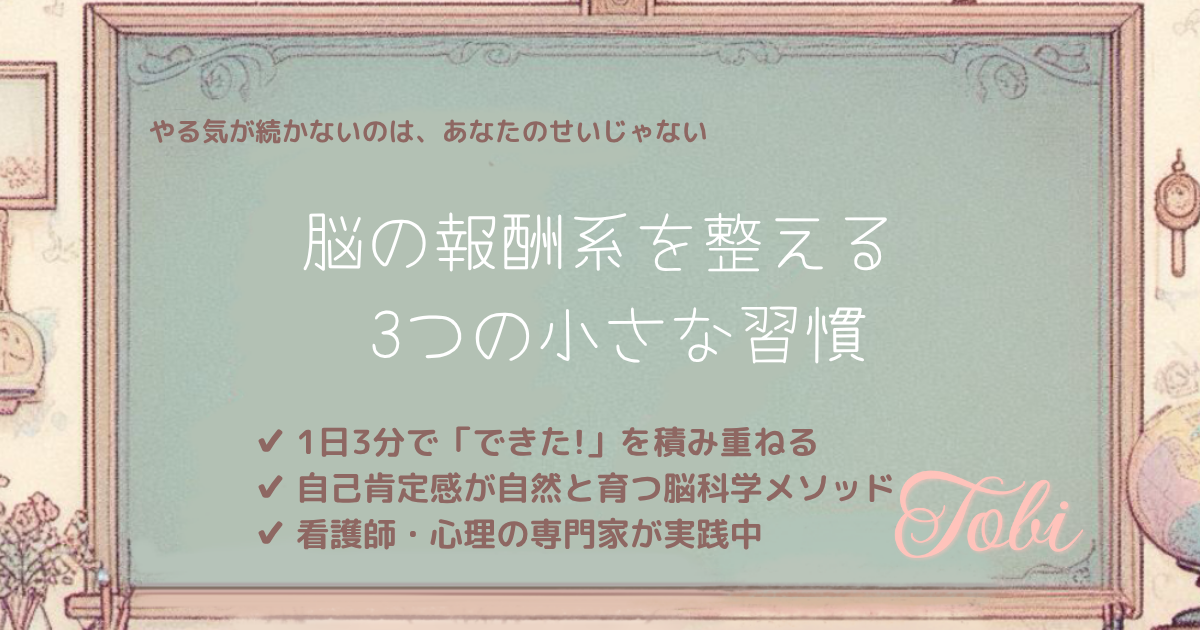



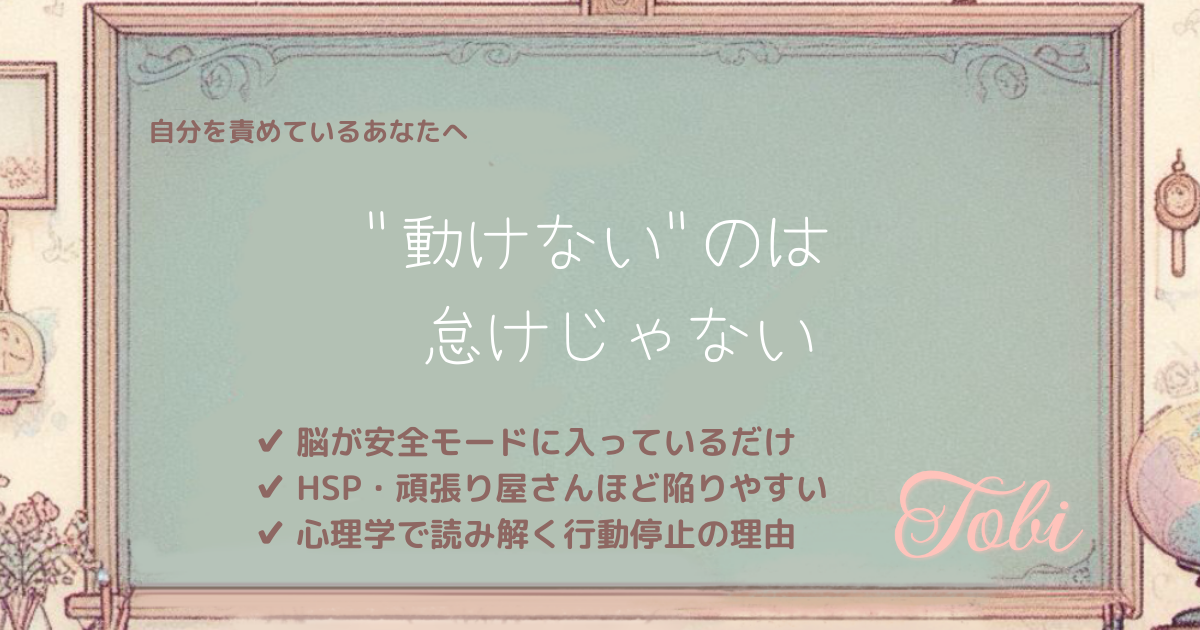

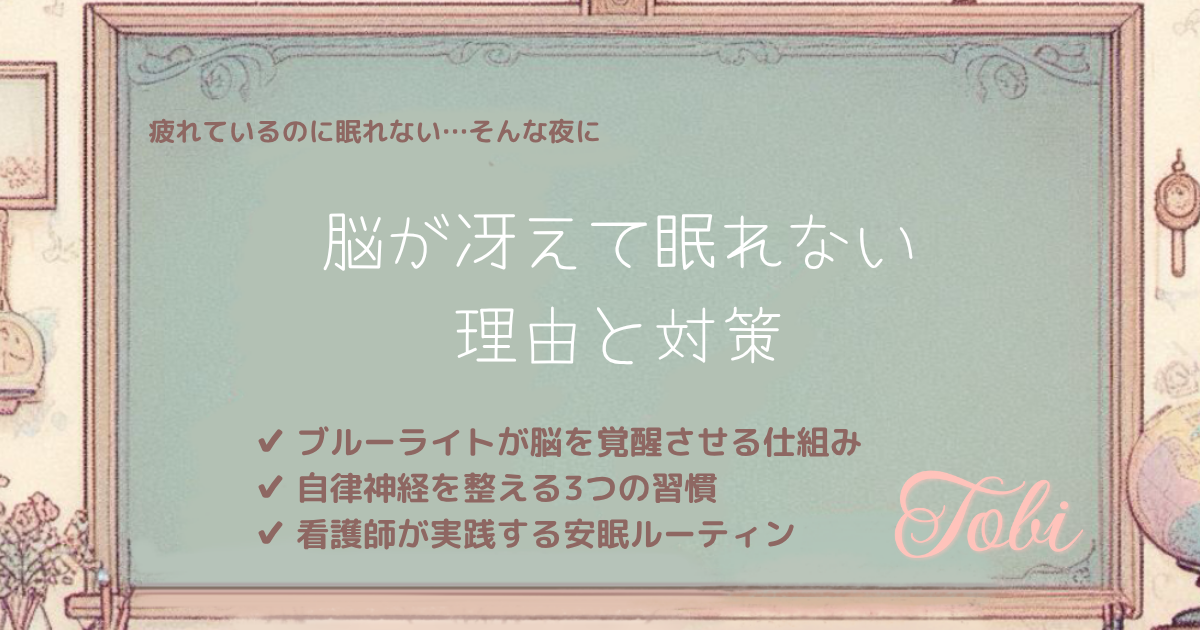
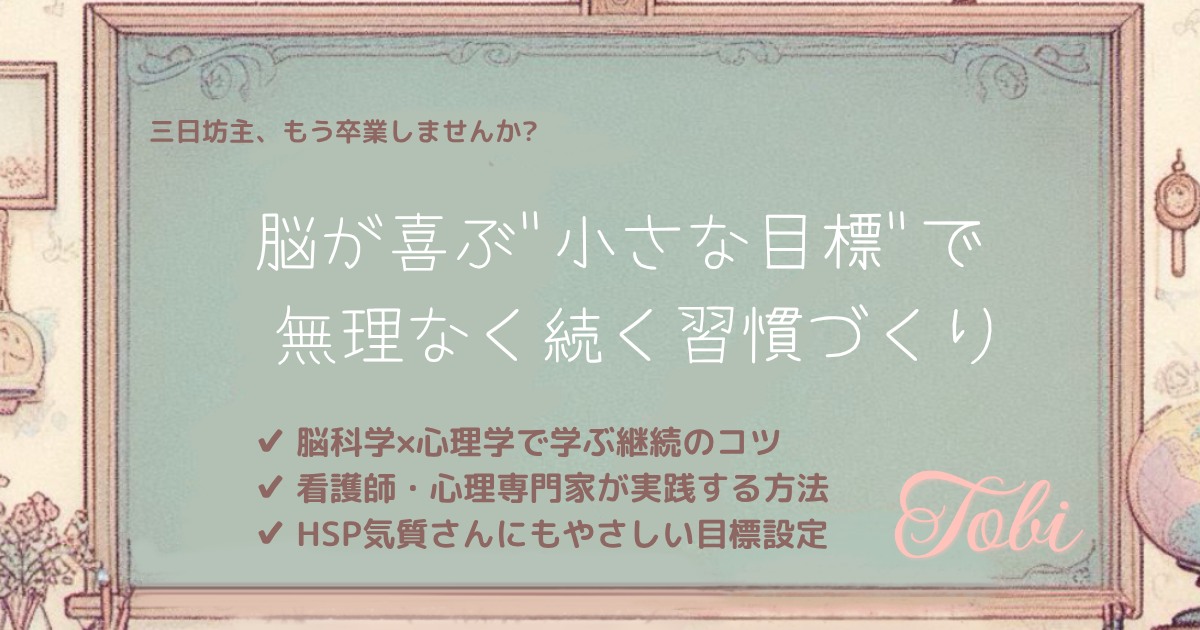
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません