「痛み、どのくらい?」に答えられない患者さん👩⚕️数値に頼らない痛みアセスメント完全ガイド

目次
😣 そのひと言、実は患者さんを困らせてるかも?
「痛みを1から10で教えてください」
看護師なら毎日のように使うこの質問。でも、患者さんが「うーん…」って困った顔をすること、ありませんか?
認知症のおばあちゃんにいつものように「痛みはどのくらいですか?」って聞いたら、「痛いのはわかるんだけど、数字って言われても…」って悲しそうな表情をされて。その時初めて気づいたんです。数値で痛みを表現するって、実はすごく難しいことなんだって。
🤔 こんな場面、心当たりありませんか?
- 「痛い」とは言うけど、具体的な数値は言えない
- いつもより表情が辛そうだけど「大丈夫」と言う
- 家族から「様子がおかしい」と言われるけど、本人は何も訴えない
実は痛みを数値化できない患者さんって、思っている以上に多いんです!
✨【答え】観察力を磨けば、数値なしでも痛みはしっかり評価できます
結論から言うと、表情・行動・生理的反応の3つの視点から総合的に観察すれば、数値化が困難な患者さんの痛みも正確にアセスメントできます!
実際に私がこの方法を使い始めてから、見逃していた痛みにたくさん気づけるようになりました。数値評価スケール(NRS)だけに頼らない観察技術は、看護師としてのアセスメント力を確実にレベルアップさせてくれますよ💪
🧠 なぜ「痛みの数値化」は難しいの?脳の仕組みから解説
痛みは「超主観的」な体験だから
痛みアセスメントが難しい理由、それは痛みが完全に「その人だけの体験」だからなんです。
例えば、同じ注射を打っても:
- Aさん「全然痛くない、1くらい」
- Bさん「めちゃくちゃ痛い!8はある!」
なんてことがよくありますよね。
🧠 脳科学的に見ると、痛みはこんな風に処理されます
- 感覚野:「どこが」「どんな風に」痛いか
- 情動系:「怖い」「不安」などの気持ち
- 認知系:過去の経験や記憶との照らし合わせ
つまり、同じ刺激でも、その人の性格、経験、その時の気分によって感じ方が全然違うってことなんです。
💡 私の「しまった!」体験談
新人の頃、腰痛で入院中の60代男性患者さんがいました。毎日「痛みは?」って聞くと、いつも「2か3かな」って答える真面目そうな方で。
でも、ある夜勤の時に偶然見かけたんです。ベッドで歯を食いしばって、額に汗をかいているその患者さんを…!
慌てて声をかけると「いや、我慢できる程度だから大丈夫です」って。でも明らかに辛そう。翌日、主治医に相談して鎮痛薬を調整してもらいました。
その時学んだこと:「我慢強い人ほど、数値は当てにならない」
それ以来、数値だけじゃなく、必ず表情や行動もチェックするようになりました。
👀 今日から使える!3つの観察ポイントで痛みを見抜く方法
🎭【ポイント1】表情観察:「顔は嘘をつけない」の法則
顔って本当に正直なんです。口では「大丈夫」って言ってても、表情には必ず痛みのサインが現れます。
✅ 今すぐチェック!痛みの表情サイン
- 眉間のしわ:無意識に力が入る
- 目の変化:細める、まばたきが増える
- 口元の変化:への字口、歯を食いしばる仕草
- 全体的な印象:いつもより険しい、ぼんやりしている
📝 私の観察テクニック:「笑顔チェック法」
入院時や初回面談の時に、患者さんのリラックスした笑顔をしっかり記憶しておくんです。写真を見るみたいに。
そうすると、「あれ?いつもの笑顔と違うな」「なんか表情が硬いな」って変化にすぐ気づけるようになります。
🚶♂️【ポイント2】行動観察:体は正直に「SOS」を出してる
痛みがあると、人って無意識に「痛みを避ける行動」を取るんです。これって本能的なものなので、隠そうと思っても隠せないんですよね。
✅ 見逃し注意!痛みの行動サイン
🔍 体位・姿勢の変化
- いつもより丸まった姿勢をとる
- 特定の部位をかばうような動き
- 同じ姿勢を長時間続けられない
🔍 動作の変化
- 歩くスピードがいつもより遅い
- 立ち座りに時間がかかる
- 階段を避けるようになった
🔍 活動パターンの変化
- いつもは積極的なのに、ベッドで過ごす時間が増えた
- 逆に、落ち着かずウロウロしている
- 食事時間が長くなった、食欲が落ちた
🏥 リアル体験談:認知症病棟での「気づき」
認知症病棟で働いていた時のこと。いつもホールで歌を歌ったり、他の患者さんとおしゃべりしたりする、とても明るいおじいちゃんがいました。
ところが、ある日から急にソファにぽつんと座って、ぼーっとしているだけに。熱もない、「痛い」とも言わない。でも何かがおかしい…
よく観察すると、歩く時に右足をそっとかばうような動きが。「もしかして?」と思ってレントゲンを撮ってもらったら、なんと圧迫骨折が見つかったんです!
言葉で表現できなくても、体は正直に「痛いよ」って教えてくれてたんですね。
📊【ポイント3】バイタルサイン:数値が教えてくれる痛みのシグナル
痛みって、自律神経にも影響するんです。なので、バイタルサインの変化も重要な手がかりになります。
✅ 痛みで変化しやすいバイタルサイン
- 血圧:上昇することが多い
- 脈拍:早くなる、不規則になることも
- 呼吸:浅く早くなる、時に息を詰める
- その他:発汗、顔色の変化、体温の微細な変動
⚠️ 大切な注意点 これらの変化は感染症や不安、薬の副作用でも起こります。なので、他の症状と合わせて総合的に判断することが重要です!
🚀 明日から実践!痛みアセスメント力をアップさせる3ステップ
📝 ステップ1:観察の「ABCD」を毎日の習慣にしよう
新人指導で必ず教えている、私オリジナルの観察法です✨
- A(Appearance):見た目・表情はどう?
- B(Behavior):いつもと行動が違う?
- C(Circulation):バイタルに変化は?
- D(Daily pattern):日常のパターンから外れてない?
📱 ステップ2:「患者さん観察メモ」を記録
私の実践法:メモ機能活用術
患者さんの「いつもの様子」を簡単にメモしてます。
例:
- 「Cさん:朝は必ず窓際でラジオ体操、廊下はスタスタ歩く、夕方に娘さんの話をよくする」
- 「Dさん:無口だけど看護師にはにっこり笑う、夜はなかなか寝付けない」
こうしておくと、「あれ?今日はラジオ体操してない」「いつもより歩くのが遅い」って変化にパッと気づけるんです👍
👂 ステップ3:周りの声に耳を傾ける「情報収集術」
家族さんや介護スタッフからの情報は、まさに宝の山!
よく聞く貴重な情報:
- 「最近、夜中によく目を覚ますみたいで…」(→痛みで眠れない?)
- 「食事の時間が長くなった気がします」(→座位保持が辛い?)
- 「いつもより口数が少なくて」(→痛みを我慢してる?)
「いつもと違う」を一番よく知ってるのは、普段一緒にいる人たちですからね。些細な変化も見逃さず、積極的に情報収集しましょう。
痛みアセスメントをもっと深く学びたい方には、こちらの専門書がおすすめです。臨床現場で実際に使われている評価法が詳しく解説されています。
💪 【まとめ】数値に頼らない痛みアセスメントで、患者さんに寄り添うケアを実現しよう
痛みアセスメント完全マスターのポイント
✅ 表情・行動・バイタルサインの3つの視点で総合判断
✅ 「いつもと違う」変化を見逃さない観察力を養う
✅ 観察の「ABCD」を毎日の習慣にする
✅ 周囲の人からの情報も積極的に活用する
✅ 完璧を求めすぎず、今できる最善のケアを心がける
🌟 一番大切なのは「その人らしさ」を知ること
痛みって、完全に数値化できるものじゃありません。でも、だからこそ私たち看護師の観察力と洞察力が本当に大切なんです。
患者さん一人ひとりに真剣に向き合う気持ちがあれば、きっと痛みのサインに気づけるはず。あなたの「気づき」と「寄り添い」が、患者さんの痛みを和らげる大きな一歩になってますよ💝
完璧なアセスメントなんて誰にもできません。 今日より明日、少しでも患者さんの気持ちに近づけるよう、一緒に成長していきましょう!
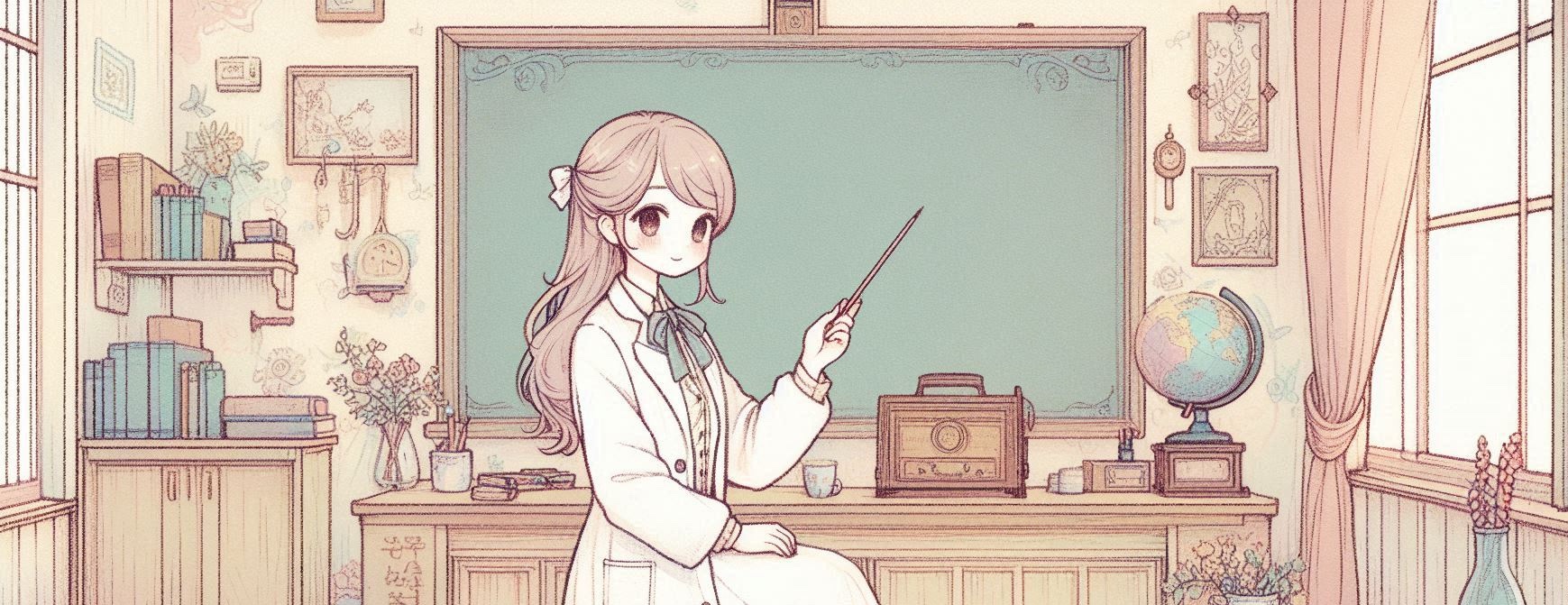
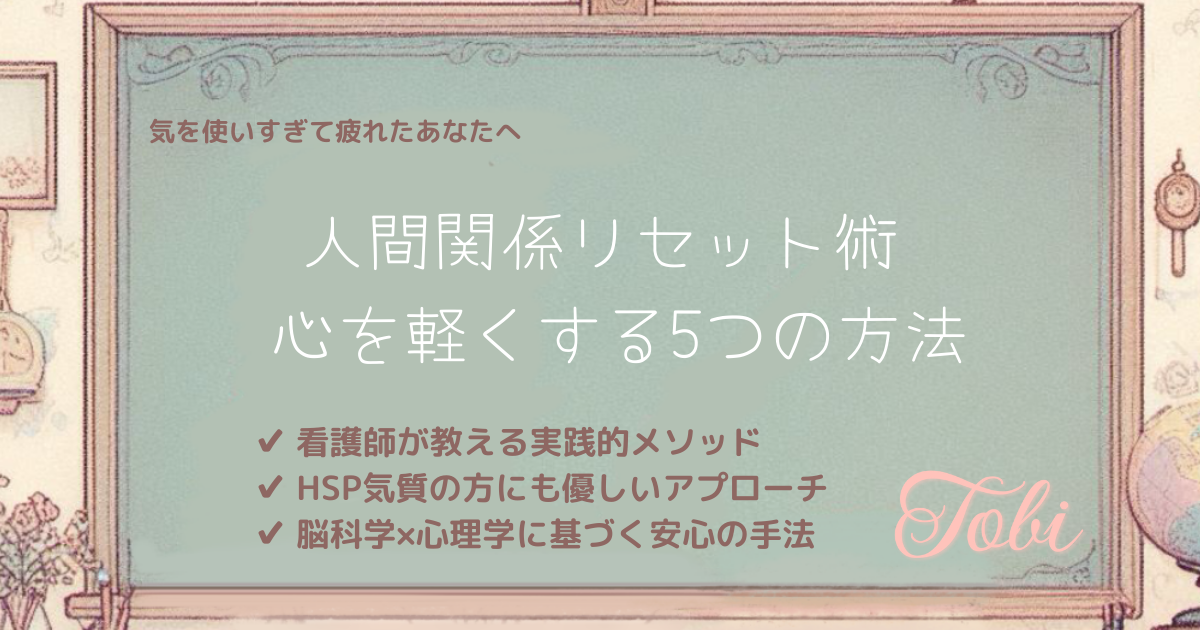
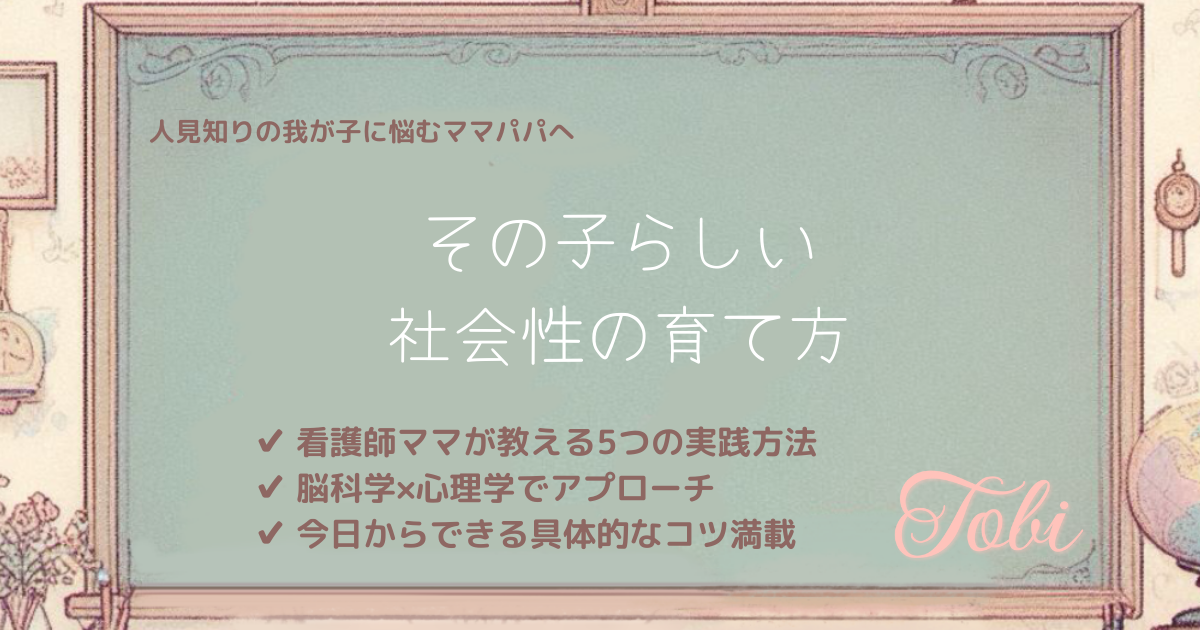


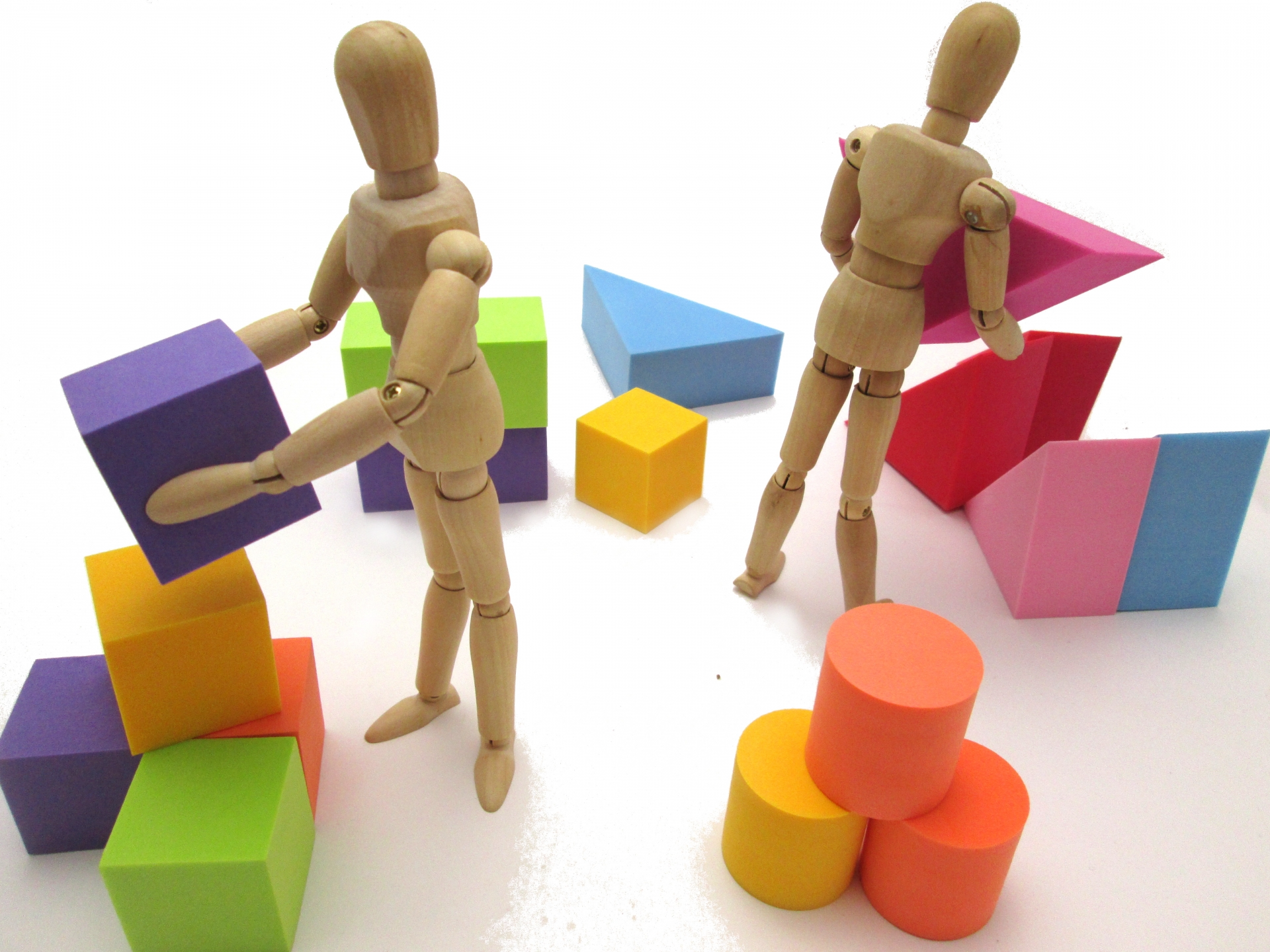

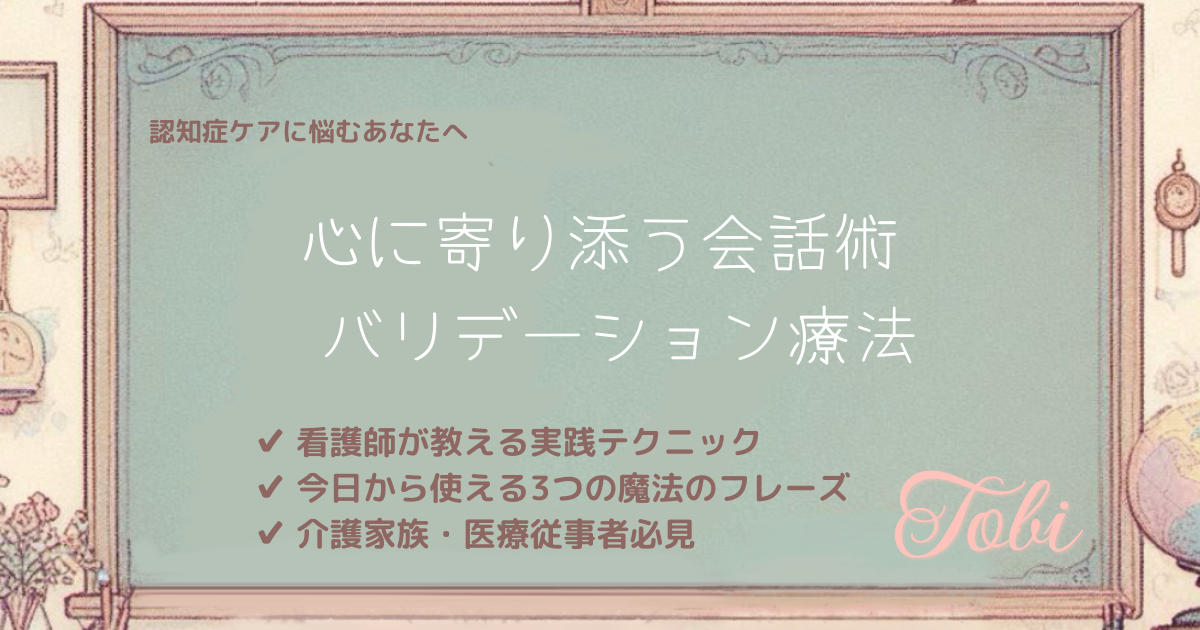

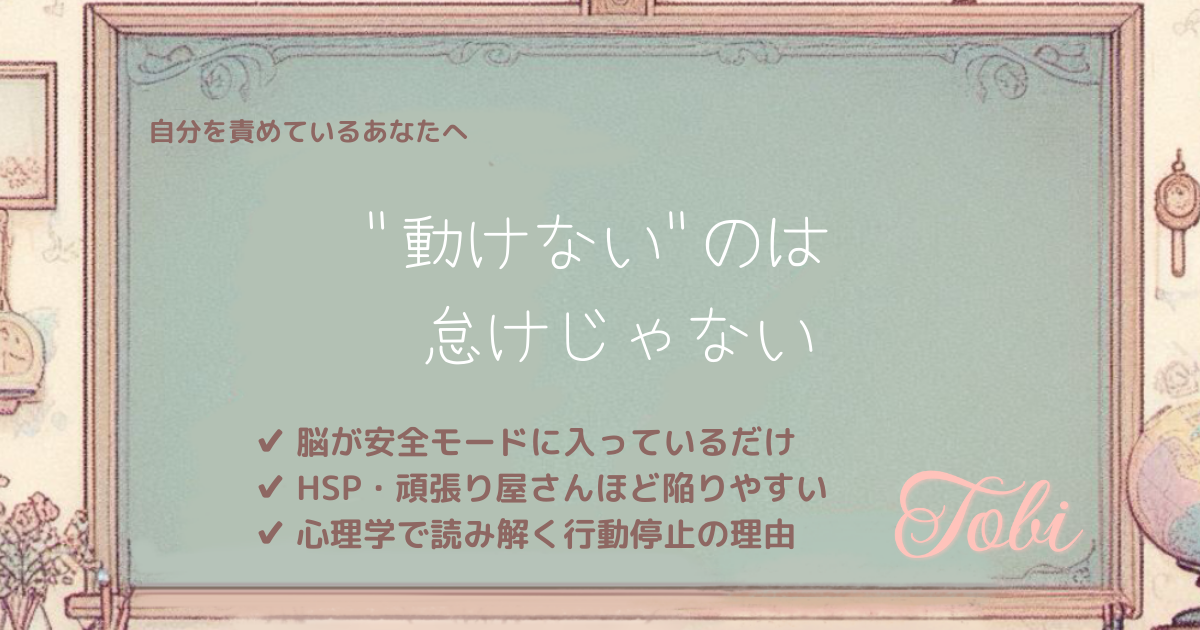

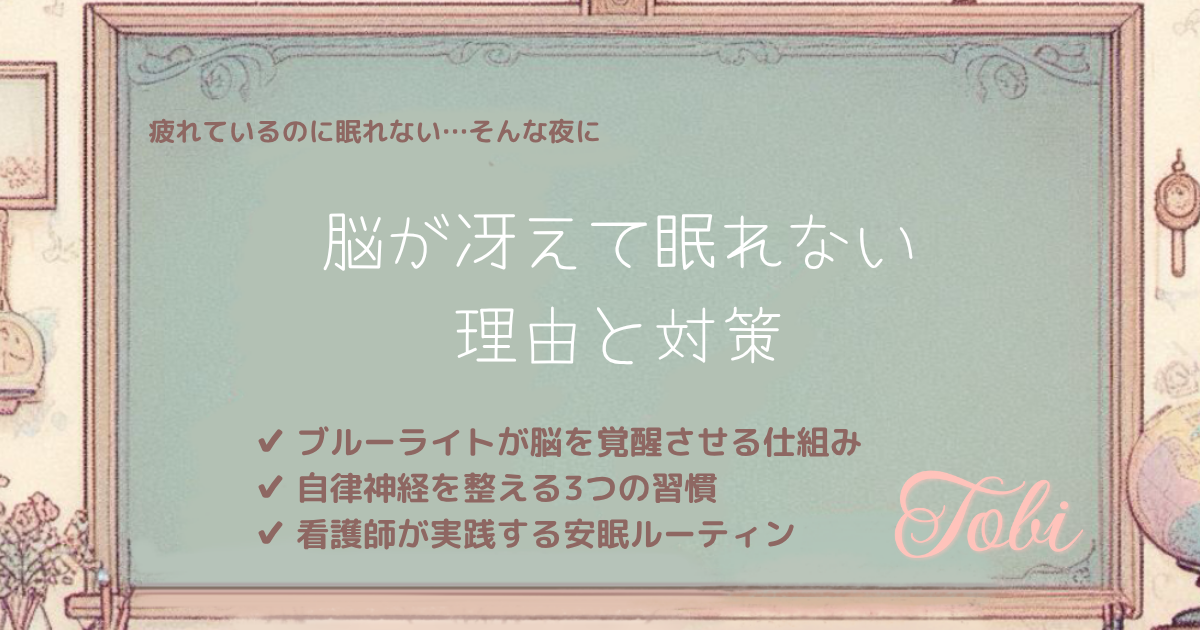
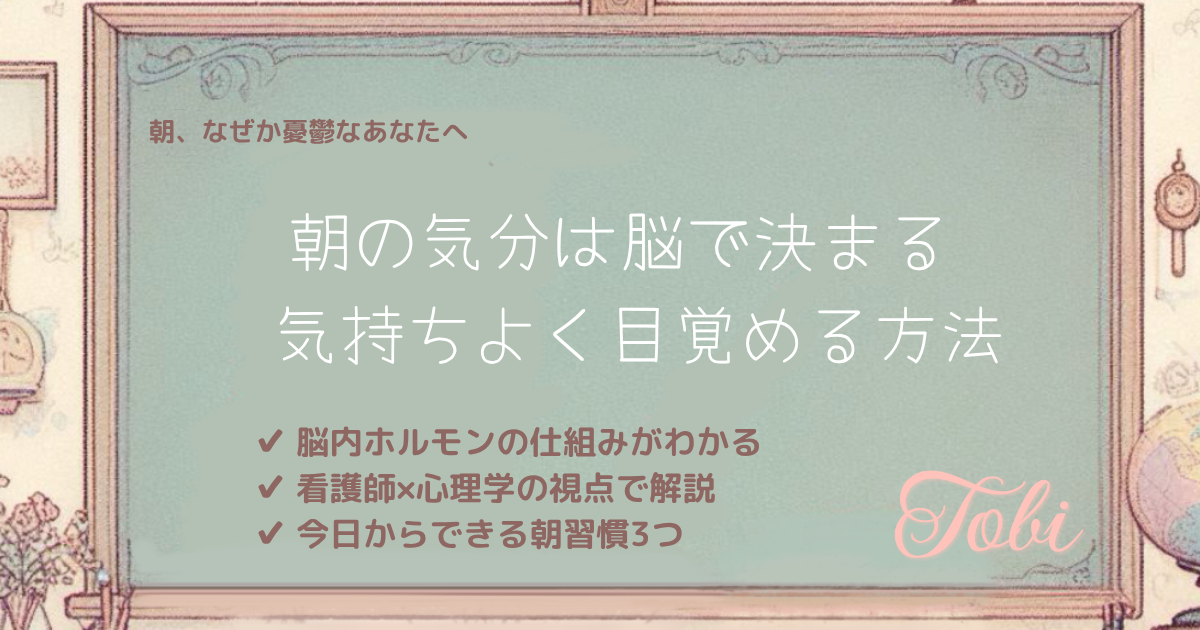
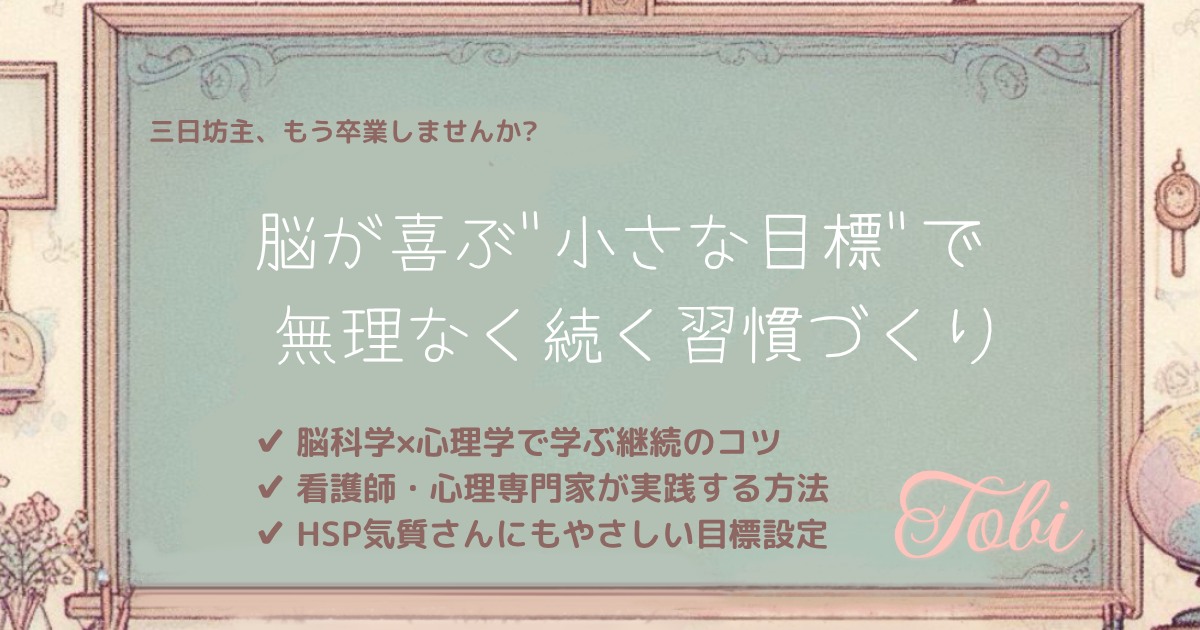
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません