子育ての疑問】褒めても言うことを聞かない子どもの心理とは?効果的な関わり方を心理学で解説

目次
🤔 「また今日も…」褒めても動いてくれない子にため息
「○○ちゃん、お片付けが上手だね〜!」
そう言ったとたん、さっきまでニコニコしていた我が子が急にふてくされてしまった…なんて経験、ありませんか?
私も看護師として小児科で働いていた頃、そして保育士として子どもたちと関わる中で、「褒めているのに、なぜか逆効果」という場面に何度も出会いました。真夜中に「私の関わり方が間違っているのかな…」と一人で悩んだこともあります。
でも大丈夫。これには実は、子どもの心理学的な理由があるんです。あなたの愛情が足りないわけでも、やり方が間違っているわけでもありません。
💡 褒め方を変えれば、子どもの反応も変わる!
褒めても言うことを聞かない子どもには、「褒め方」ではなく「関わり方」を変えることが効果的です。
心理学の研究によると、子どもには「自分で決めたい」という強い欲求があり、従来の褒め方では逆に「コントロールされている」と感じてしまうことが分かっています。
つまり、子どもの内側からのやる気(内的動機)を大切にする関わり方にシフトチェンジすれば、もっと自然で効果的なコミュニケーションが取れるようになります。
🧠 なぜ「褒めても効かない子」がいるの?心理学で紐解く子どもの心
📊 自己決定理論で分かる!子どもの3つの基本欲求
アメリカの心理学者エドワード・デシ博士が提唱した「自己決定理論」によると、すべての人間(もちろん子どもも!)には3つの基本的な心理的欲求があります。
| 欲求の種類 | 具体的な内容 | 子どもの行動例 |
|---|---|---|
| 🎯 自律性 | 自分で決めたい | 「自分でやる!」と主張する |
| ⭐ 有能感 | できる実感を持ちたい | 難しいことにチャレンジしたがる |
| 💝 関係性 | つながりを感じたい | 認められたい、理解されたい |
特に「自律性」の欲求が強い子は、大人からの褒め言葉を「やらされている感」として受け取ってしまうことがあります。
🎭 実体験エピソード:保育園のAくんのケース
5歳のAくんは、とても繊細で創作活動が大好きな男の子でした。ある日、素敵な絵を描いていたので「上手に描けたね!すごいじゃない!」と褒めたところ、急に筆を投げ出して「もうやめる…」と言い出したんです。
でも後日、「どんな色を使ったの?」「この部分はどんな気持ちで描いたの?」と質問形式で関わってみると…目をキラキラ輝かせながら「ここは夕焼けの色でね、ここは僕の好きな海の色なんだ!」と嬉しそうに説明してくれました。
この違いは何でしょうか?
- ❌ 外的動機型の褒め方: 「上手だね」→ 大人の評価が基準
- ⭕ 内的動機を引き出す関わり方: 「どんな気持ち?」→ 子ども自身の体験が基準
🌸 HSP気質の子どもは特に敏感
看護師時代に出会った多くの子どもたちを観察していると、HSP(Highly Sensitive Person)の特性を持つ子(HSC)は、褒め言葉の裏にある大人の期待や感情を敏感にキャッチします。
「褒められた=また頑張らなきゃいけない」 「期待に応えられなかったらどうしよう…」
そんな不安を感じて、褒め言葉から距離を置こうとすることも多いんです。
📈 年齢別:褒め言葉の受け取り方の変化
| 年齢 | 特徴 | 効果的なアプローチ |
|---|---|---|
| 2-3歳 | 素直に褒め言葉を受け取る | シンプルな称賛でOK |
| 4-5歳 | 自我が発達、「自分で!」が強まる | 過程に注目した声かけ |
| 6歳以上 | より複雑な心理状態 | 質問型・選択肢提示型 |
🌟 今日からできる!「響く関わり方」3つの実践テクニック
1️⃣ 「結果褒め」から「過程褒め」へシフト
❌ Before(結果褒め):
- 「お片付けができて偉いね!」
- 「宿題が終わってすごいね!」
⭕ After(過程褒め):
- 「最初は嫌そうだったけど、最後まで頑張ったんだね」
- 「難しい問題もあきらめずに考えたね」
私自身、この声かけに変えてから、子どもたちの表情が明らかに柔らかくなることを実感しました。結果ではなく、その子の努力や工夫に光を当てることで、子ども自身が自分の頑張りを客観視できるようになります。
2️⃣ 「評価」ではなく「質問」で気持ちを引き出す
🎯 効果的な質問例:
- 「今、どんな気持ち?」
- 「一番頑張ったのはどこかな?」
- 「やってみてどうだった?」
- 「次はどうしてみたい?」
質問することで、子ども自身が自分の体験を振り返り、内側からの満足感を味わえます。これが本当の自信につながるんです。
3️⃣ 「指示」から「選択肢」へ変換
❌ Before(指示型):
- 「お片付けしなさい」
- 「宿題をやりなさい」
⭕ After(選択肢型):
- 「おもちゃから片付ける?それとも本から?」
- 「宿題は先にする?それとも少し休んでから?」
小さな選択でも、子どもの自律性を尊重できます。「自分で決めた」という感覚が、行動への主体性を育てます。
この関わり方についてもっと詳しく学びたい方は、子どもの心理学や発達について書かれた専門書もおすすめです。特に下記の褒め方の本は実践的で分かりやすく、多くの保護者や教育関係者に愛読されています。
💖 まとめ:子どもの心に寄り添う関わり方で、毎日がもっと楽しくなる
✨ 今日のポイント5つ
✅ 褒めても響かない子は「自律性」の欲求が強い可能性
✅ 「結果褒め」より「過程褒め」で子どもの努力に注目
✅ 質問形式で子ども自身の気持ちを引き出す
✅ 選択肢を提供して自律性を尊重
✅ HSP気質の子には特に繊細な配慮を
🌈 一番大切なメッセージ
「その子らしさ」を理解しようとする、あなたの愛情が一番の魔法です。
子育ても教育も、正解は一つじゃありません。だからこそ迷うし、悩むし、時には疲れてしまいます。でも、だからこそ一人ひとりの子どもの個性や特性を大切にできる、とても価値のある時間なんです。
今日学んだことを「ちょっと試してみようかな」という軽い気持ちで実践してみてください。きっと新しい発見があるはずです。
あなたの毎日が、子どもたちとの温かいやり取りで満たされますように。
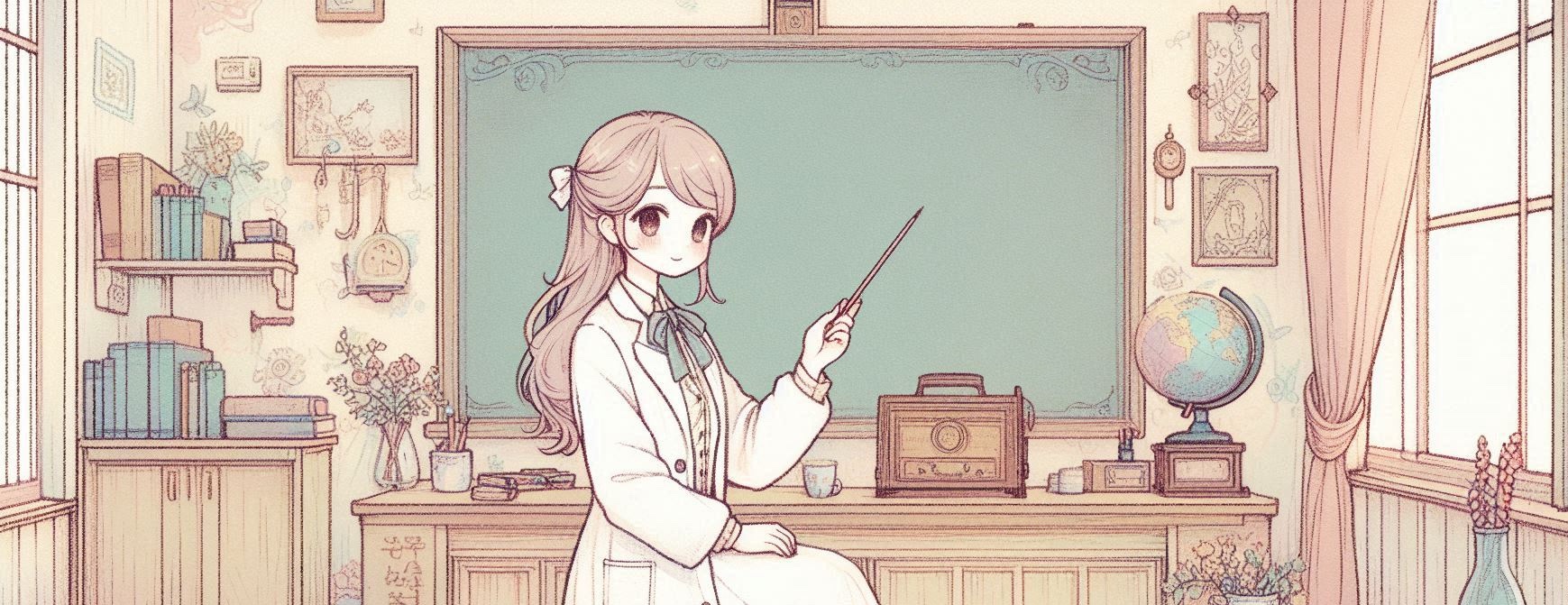
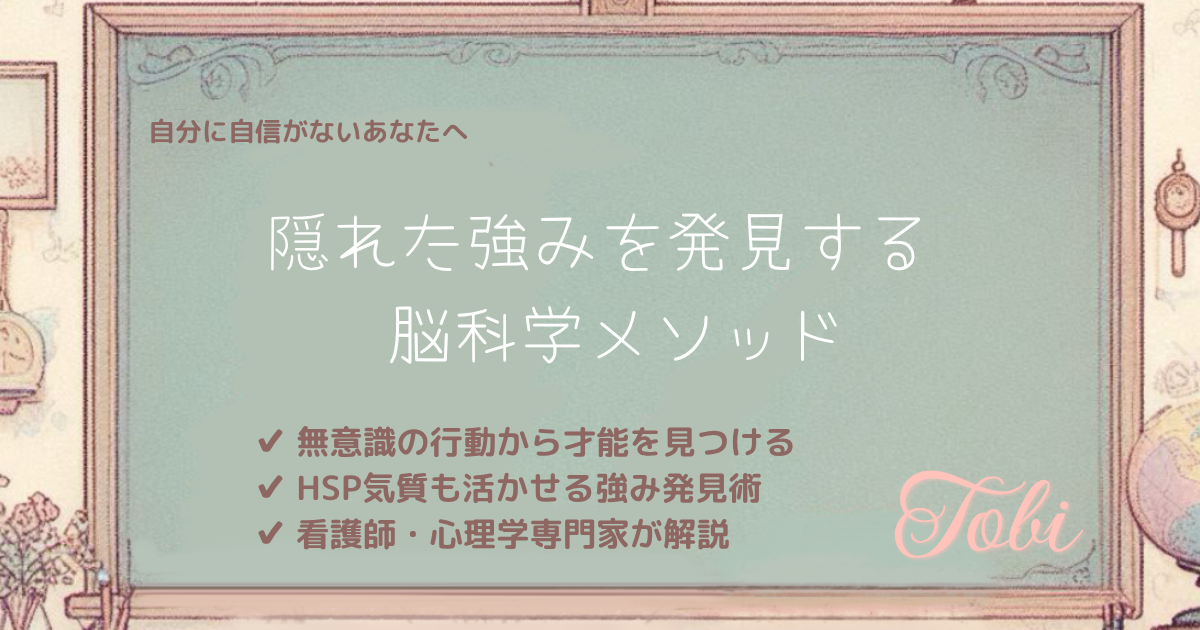



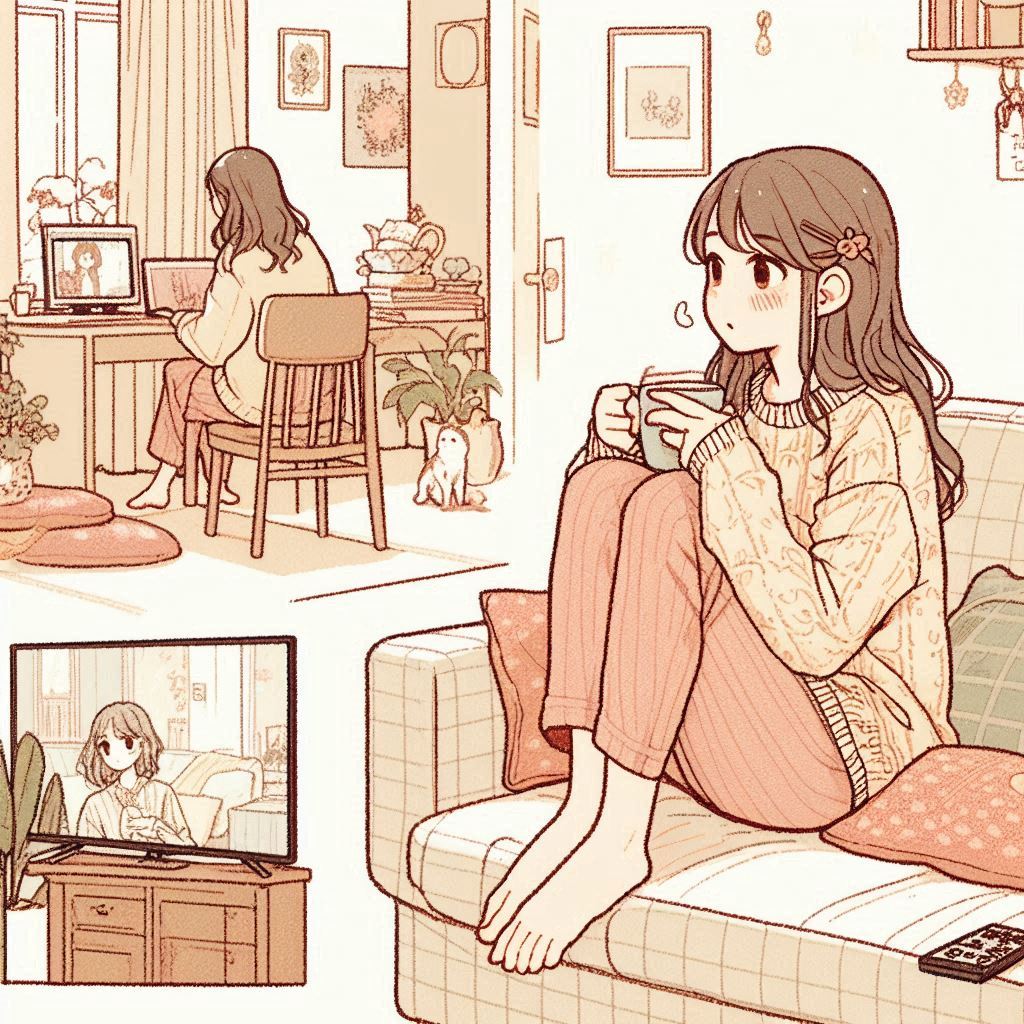

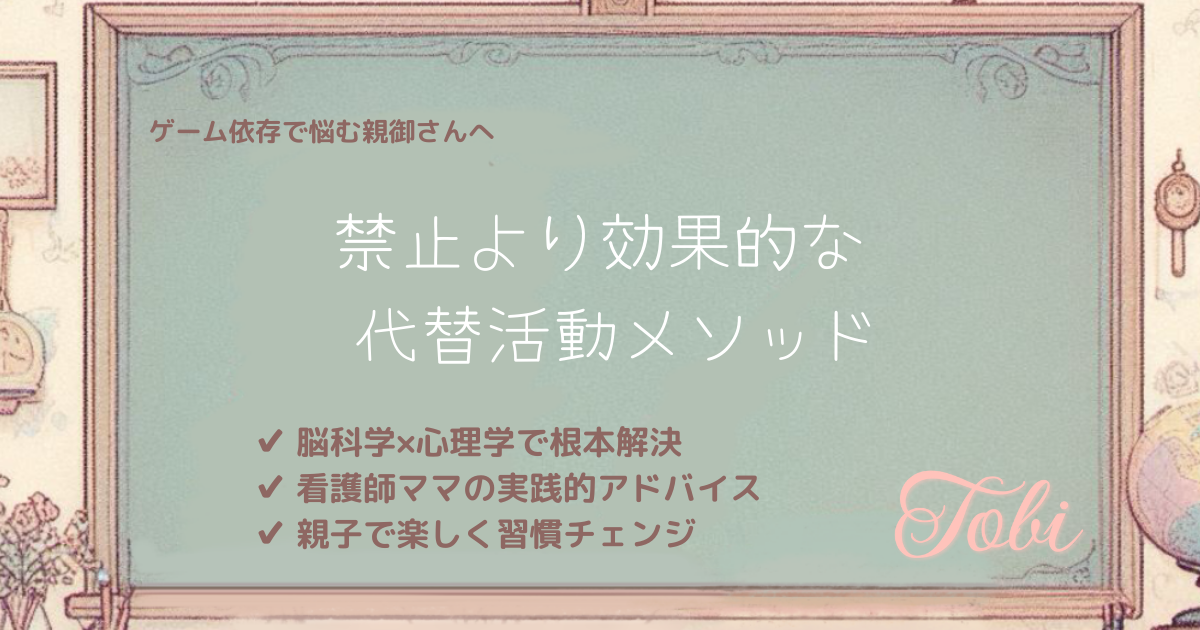

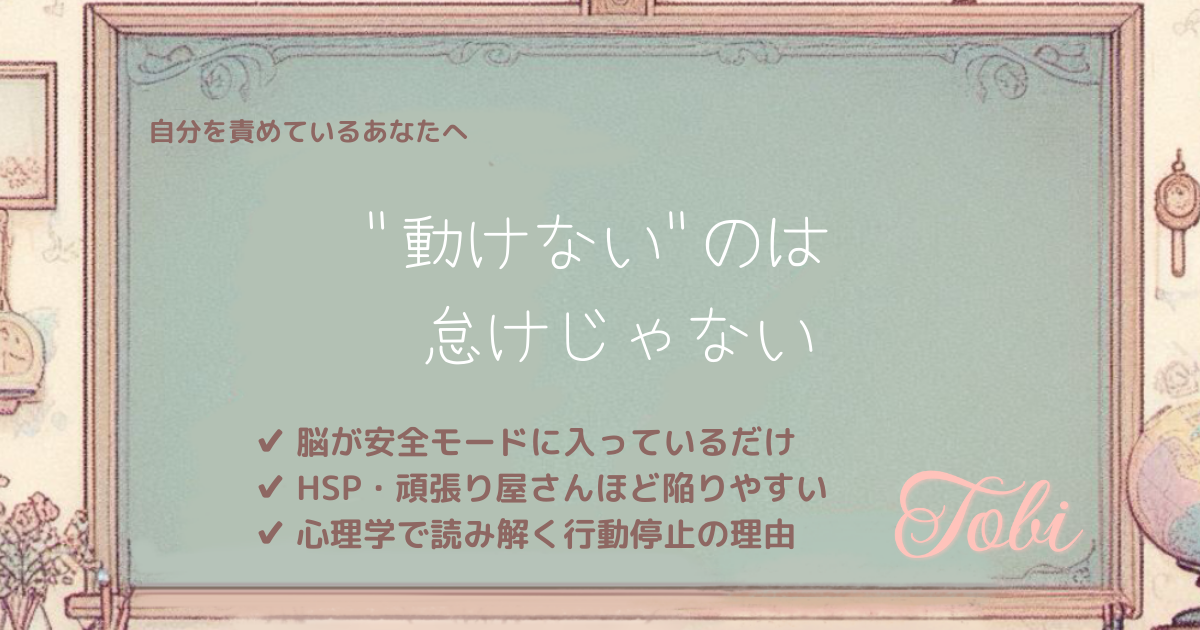

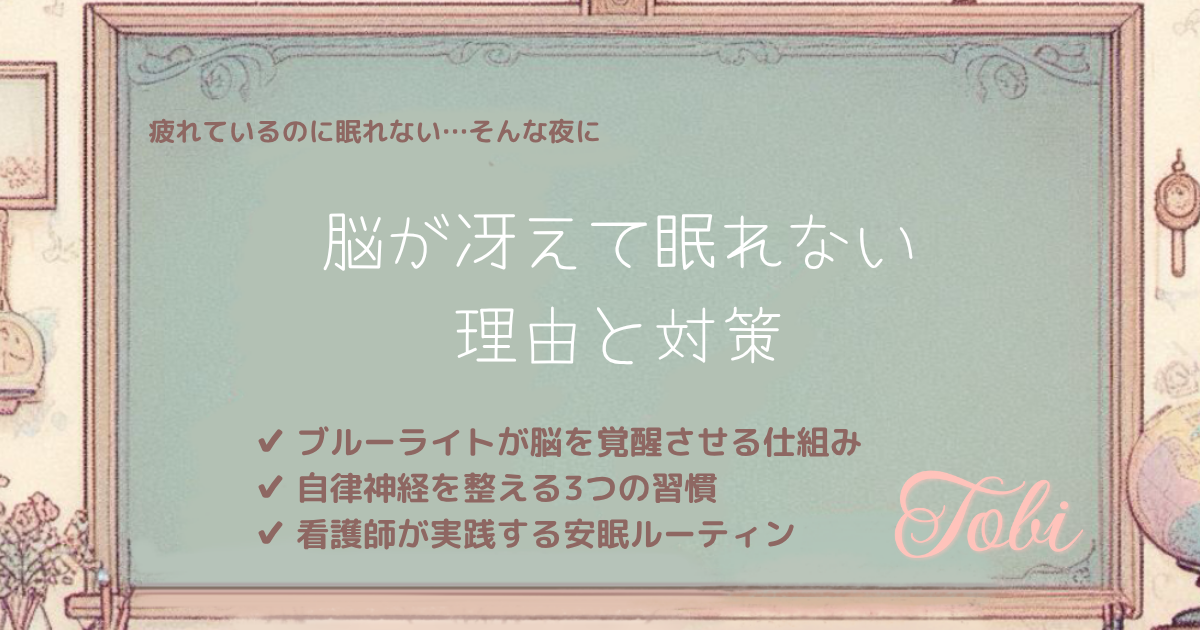
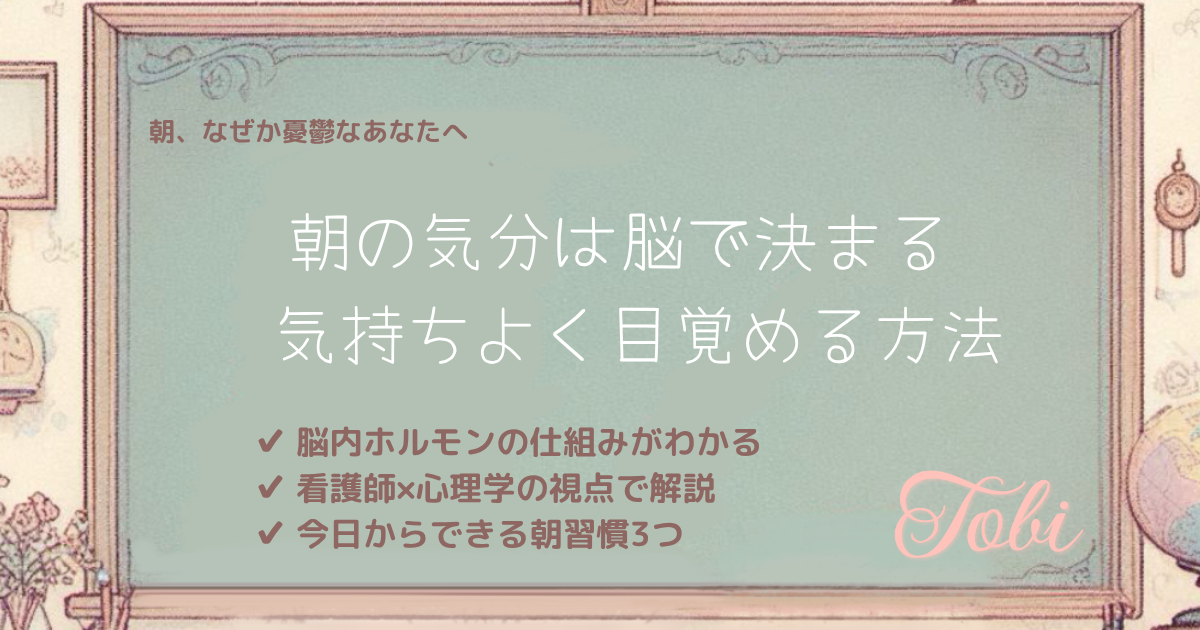
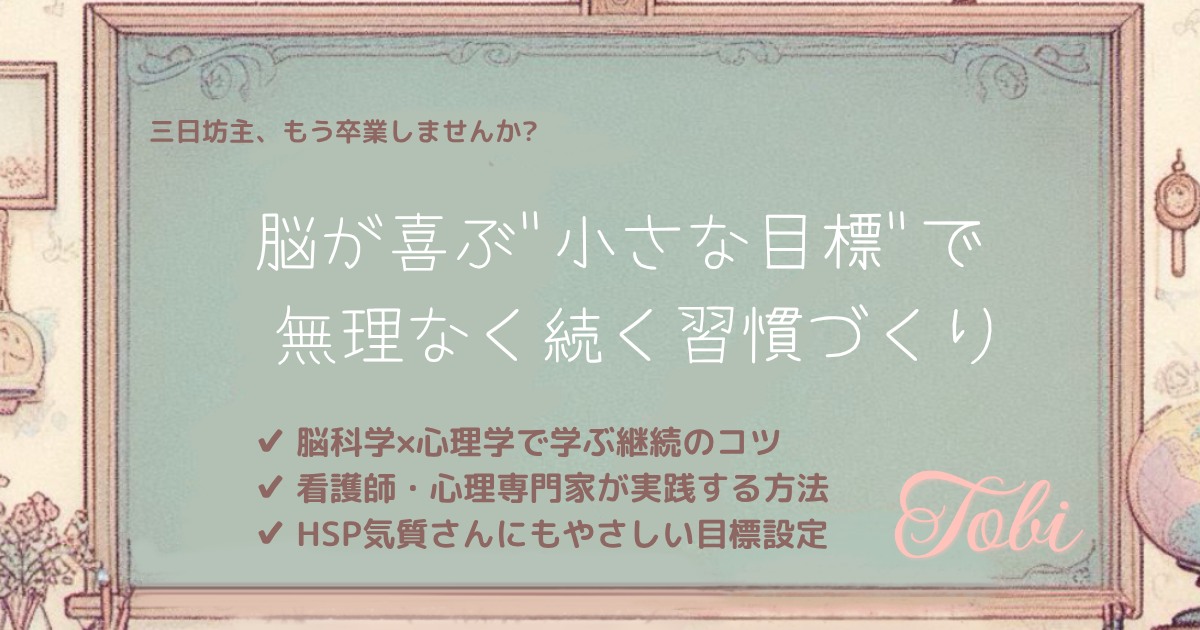
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません